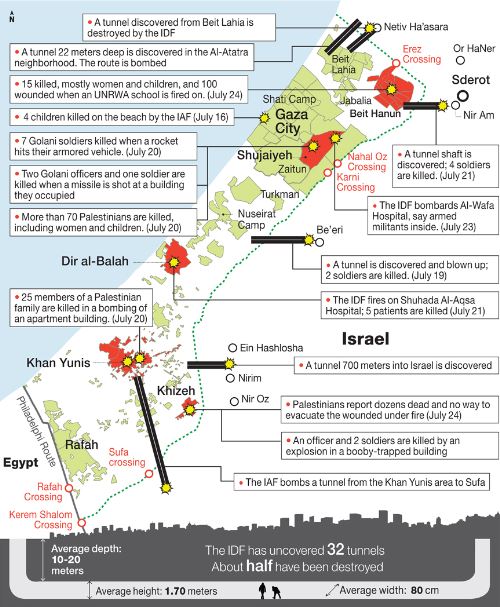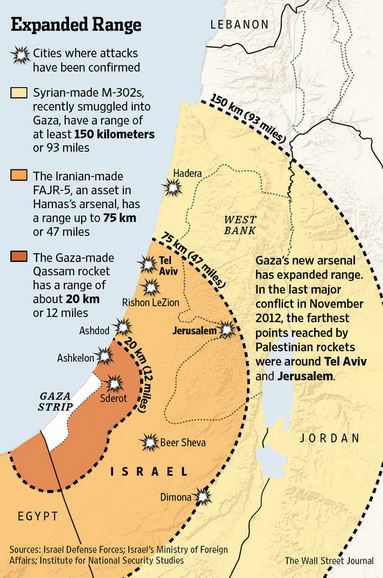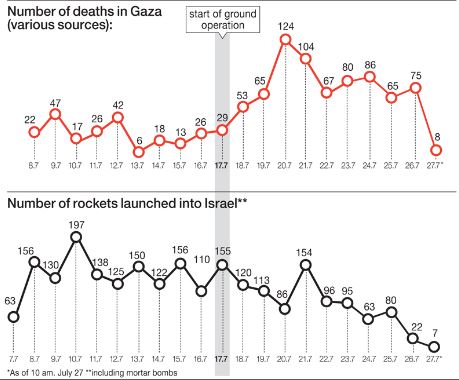本日の未明に、『フォーサイト』にイラン核開発交渉と、ガザ紛争の背景と構図についての論稿が掲載されました。
池内恵「イラン核開発交渉は延長の見通し、ガザ紛争は置き去りに」『フォーサイト』2014年7月16日
ほとんど時差のないリアルタイムの情報に基づく考察です。
歴史系・思想理論系の論文で机に向かい続けていると、つい息抜きに現状分析の情報整理をしたくなるものですから、寄稿の頻度が上がっています。実際に中東現地の動き、中東をめぐる国際政治の動きが非常に速いですので、きちんと記録しておかないと、気づいたら昔が思い出せないほど変わっていたということになりかねません。
イラン核問題交渉の展開については、前日の下記の論稿からの続き物としてお読みください。
池内恵「期限切れ目前のイラン核開発交渉─ロスタイムに劇的に決まるか、延長戦か」『フォーサイト』2014年7月15日
いずれも有料なので購読していない人には申し訳ないのですが・・・考え物ですね。有料にしておくと、専門家や官僚やメディア関係者の間には購読者が多いので、実際に必要とする人に絞り込んで情報を拡散できるのですが、問題はそんなもの読まずに、お金かけずに情報を求めるメディア関係者も多いこと。「記者クラブ」みたいなところで情報が一元管理されていてメディア企業の人には無料で一方的に教えてくれる、ということに慣れているメディア関係者が多すぎるのです。
中東関係だと、いくつかそういう窓口みたいなのがあって、タダで愛想よく教えてくれる(裏ではぶつくさ、いやすごい悪態ついていたりしますが)、出向いてくれる、電話を受けてくれる便利な「専門家」の話が、かなり無茶なものでもメディアに出回って、「真実」ということになってしまう。
ですのである程度無料で標準的な知見を出しておかないと、日本での議論がすごい変なところに行ってしまう。しかし重要なものをどんどん無料にしていたら購読する人はいなくなる。
一定のタイムラグで無料公開する、といった手段を当分とるしかないのかな・・・
それより前には、頑張って英語で読むなら、私の論稿を読まなくても同様の解説が読めるよ、ということで新聞記事等を紹介しておくといいかもしれない。このブログでこれまでもやってきたことなのですが。
今回の寄稿では、イラン核開発交渉に関しては、最低限踏まえるべき二つの記事にリンクを張っておいた。
一つは15日にウィーンを発って、カイロに向かわずワシントンでオバマと協議すると述べたケリーの記者会見の発言。通信社や新聞各紙が解説していますが、原文そのものに当たるのがいいでしょう。
もう一つはイランの交渉担当者のザリーフ外相がウィーンで14日にインタビューに応え、15日朝のニューヨーク・タイムズ紙一面に載った「妥協案」についての記事(David E. Sanger, Iran Outlines Nuclear Deal; Accepts Limit, The New York Times, July 14, 2014)。こちらは有料だが月に何本か無料で読めるはず。また、大学などに属していれば、大学内から新聞記事データベースにアクセスできることが多いはずだ。ニューヨーク・タイムズはそこから読めるはずだ。ウォールストリート・ジャーナルなどはデータベースで読めない場合もあるが。
オバマ大統領との協議がどのようになるかというと、おそらく交渉打ち切り・制裁再強化を主張する議会関係者に対して一定の進展があったと示して延長に同意させるということなのだろう。双方に妥協する意思は大いにあるが、7月20日までには無理、といった調子のコメントが米側からもイラン側からも漏れてくる。
さて、今回はガザ紛争についても合わせてまとめておいた。こちらのテーマについては本文中にリンクはあまり貼っていないので、例えば下記のテーマについて、これから挙げる記事でも読んでみると良いだろう。
①今回の衝突の発端となったヨルダン川西岸のユダヤ人入植地での3人の少年の誘拐・殺害事件について、イスラエルのイスラエルの国内治安局シン・ベトが犯人としてカワースメ族の二人の名を挙げ、彼らがハマースのメンバーだと断定してハマースに責を帰している。しかし実際にこの二人がハマースの一部なのか、ハマースが組織として少年3人の殺害を行ったと言えるのかというと、イスラエル側の説明はあまり説得力がない。多分実態をよく反映していると思えるのが次の記事。
Shlomi Eldar, “Accused kidnappers are rogue Hamas branch,” al-Monitor, June 29, 2014.
まあハマースはパレスチナの乱暴者を集めてある意味で「更生」させて「正しい目的」(=イスラエルの破壊)のために戦えと教えて戦闘員を集めて台頭してきたわけで、こういういわくつきの一族であっても、彼らがイスラエルと紛争を起こせば彼らを擁護しないといけなくなる。
ただ、実効支配していないヨルダン川西岸の、組織の最末端になると実際に統制しているわけではないので、「関係ない」「知らない」というのは多分嘘ではなく、発端の事件に関しては本当に知らないのだろう。
しかしイスラエルがカワースメ部族を追及すれば、ハマースは彼らの側について見せないといけなくなる。ハマースは結局「用心棒の親玉」であって、「ふがいなくなったファタハと違って、誰かがイスラエルにやられたらやり返しに行ってくれる」というところで支持を集めてきたのだから、イスラエルが「ハマースの責任だ」と宣言した場合には「違います、無実です」と言うのではなく「受けて立つ」という姿勢を見せないといけない。まあそれを止めない限り和平の当事者にはなれないわけだが。
そうなるとイスラエルは「やはりハマースがやったか」ということになって、いろいろな歩み寄りの試みも全部帳消しにして掃討作戦をやるので、結局相互にエスカレートする。
もちろんカワースメ族の中には穏健派もいればハマースに正式に加わって活動してきた者もいる。しかし、手の付けられない過激派の一派がカワースメ族から現れて、それが起こした犯行がハマースの責に帰され、それによって歴代のハマース幹部がイスラエルによって報復として殺害されてきた。今回も「いつもと同じストーリー」なのである。
②疑われているのは、ネタニヤフ政権が、当初から犯人が刹那的な誘拐・殺人を行ったことを知っていながら、この事実を伏せ、ハマースが組織的に人質略取を行って政治的要求を突き付けてくるかのように印象づけてヨルダン川西岸で大規模な捜索・検挙を行ったのではないか、という点だ。
6月15日の報道ではすでに警察への通報電話があったことが知られていたが、報道管制もあり、電話の内容が詳細に知られていなかった。
Ben Hartman, “One of abducted Israeli teens called police: ‘We’ve been kidnapped’,” Jerusalem Post, June 15, 2014.
ところが、電話の録音が存在することが分かり公開されると、なんと電話をかけている間にも銃撃音と犯人の叫び声が聞こえる。警察は少年たちが殺されていたことを最初から知っていたが、ネタニヤフ政権が情報を押さえてヨルダン川西岸の大量検挙を進めたのではないか、という疑惑が浮かんだ。
Ben Hartman, “LISTEN: Recording of kidnapped teen’s distress call to police released,” Jerusalem Post, July 1, 2014.
この点に関して、ニューヨークのユダヤ系新聞『フォワード』のコラムニストのゴールドバーグ氏の考察が興味深い。
J.J. Goldberg, “How the Gaza War Started — and How It Can End,” Forward, July 10, 2014
イスラエルでは進行中の軍事作戦や治安出動について報道禁止措置を取ることがあり、イスラエルの新聞・雑誌は知っていても書きにくくなる。しかしイスラエル人はアメリカのメディアやジャーナリストと密接につながりがあるので、欧米の主要紙の知り合いに書かせてそこから「引用」する形で報じることになる。『フォワード』は、ニューヨークの下町のデリとかに行くとおいてあるような新聞だが、やはり関心が高く関係が深いので中東に関する議論の質は高い。よそが書いていないというのを見極めてここで書いたりするのだろう。ときどきすごくいい知見・視点が載っている。また、『フォワード』の場合、書き手によっては「(イスラエルではなく)アメリカこそ約束の地だ」とするタイプのユダヤ人知識人の書き手が多いので、イスラエルに対しても独特の見方をする。
この記事などを読むと、ネタニヤフ政権は少年3人の誘拐・殺害が計画的・組織的なものではないことを知りながら、これを機会にヨルダン川西岸のハマース構成員の大規模検挙に走り、また、ファタハとハマースの挙国一致政権を葬ろうとしたのではないか、という疑念が深まる。
検挙されたヨルダン川西岸のハマースの幹部の一部は、イスラエル兵ギラード・シャリートを人質に取って交換で釈放させたパレスチナ側の1000人超の囚人。要するに機会があれば取り戻そうと作戦を練っていて、今回の事件を口実に拘束して、帰さない、とハマース側が硬化するのは想像できる。
それにしても1:1000の比率での囚人・捕虜交換というのもすごいね。これがレバノンのヒズブッラーとの間だと、交換で帰ってきたイスラエル兵の「捕虜」は、「死体」の形で渡されたりする。殺害してしまってから保存しておいて、生きているかどうかわからないようにして捕虜交換の交渉するんですね・・・イスラエル側も多分死んでいると予想しながら交換に応じたりする。放ってもまた捕まえればいいと思っているのか。なんというかbizzareな光景がたまにあるのが中東。たまにじゃないか。
③さて、次がエスカレーションの段階。ヨルダン川西岸でハマース構成員がどんどん逮捕されていくのを見て、ハマース政治部門や軍事部門は地下に潜った。犯行グループの実態やイスラエルの意図をどれだけ把握していたか知らないが、とにかく危機を感じたら身を潜めて攻撃に対処するのがデフォールトなのだろう。するといつものことなのだが、ハマースの統制が緩んだと感じて、イスラーム・ジハード団など小規模の過激派がロケット弾をイスラエルに打ち込んで存在をアピール→これもいつものことだが、イスラエルはイスラーム・ジハード団であれ何であれ、ハマースの支配領域から撃たれたロケット弾は全てハマースの責任とみなして、ハマースの人員・施設を爆撃する→ハマースは当然反撃するという形でエスカレーションが進んだ。この辺りまで、上記の『フォワード』の記事はカバーしている。ユダヤ人向けの文章だから基礎的なところはすっ飛ばしているし、皮肉や諦めや嘆きなどが文章の中に盛り込まれているので読みにくいかもしれないが。何となくイディッシュっぽい文体です。饒舌な口語体。
④エジプトは14日夜に突如「停戦案」を出したが、これが一方的過ぎて仲介になっていない。双方が翌15日朝9時から軍事行動を停止する、としつつハマースが要求するガザ封鎖の緩和の期日はあいまいで、イスラエルがヨルダン川西岸で拘束した囚人の解放にも触れていない。現在のエジプトの政権のイスラエル寄りの姿勢は著しく、ムバーラク政権の時とも違う。もちろん2012年11月の停戦の際のムルスィー政権とも全く違う。
ムスリム同胞団を「テロ組織」に指定して全面闘争を繰り広げるスィースィー政権は、ハマースを目の敵にしている。ムバーラク政権も保っていたハマースとのパイプが、スィースィー政権できわめて細くなっているのは間違いない。カイロに「籠の鳥」にしているムーサー・アブーマルズーク氏だけが「停戦交渉をしている、ハマースはそろそろ受け入れる」という情報を出し続けているのだが、たぶんエジプト政府に言わされているだけで、ハマース首脳にもエジプト政府に対しても影響力・発言力がないんだろうな、というのが透けて見える。
「エジプト政府はハマースとまともに連絡を取っていない、取れていないのではないか」「イスラエルとエジプトがアメリカを疎外して反ハマースで団結している」ということを、今日の朝3時ごろの私の記事では書いておいたが、イスラエルのリベラル紙『ハアレツ』が日本時間午前8時頃(現地2時台)にウェブにアップした記事では、この点を詳細に書いてくれている。ハアレツは契約をしないとまったく記事を読めないので、一部抜粋しておこう。
Barak Ravid and Jack Khour, "Behind the scenes of the short-lived cease-fire, While the Egyptians hammered out a deal with Netanyahu, Hamas and most of the Israeli cabinet were kept out of the loop, Haaretz, Jul. 16, 2014.
エジプトが14日夜に突如発表した停戦案の策定過程からは、ハマースも、ネタニヤフ政権の外相も外され、そしてアメリカのケリー国務長官も避けられていた、という。
「アメリカの仲介はいらない」というのはもしかすると筋の通った立場かもしれないが、紛争の片方の当事者を除いて議論していては、停戦とは呼べないだろう。むしろ「対ハマースの連合協議」と言った方がいい。
14日夜のエジプトの停戦案を閣僚たちはテレビ・ラジオを通じて知って茫然。
The Egyptian cease-fire proposal that was published Monday night took most members of the diplomatic-security cabinet by complete surprise. Economy Minister Naftali Bennett heard about it in a television studio moments before going on air. Foreign Minister Avigdor Lieberman heard about it on the radio.
特に、ネタニヤフと仲たがいして、与党リクードから会派離脱しつつ連立は維持しているリーバーマン外相は全く蚊帳の外だったという。
A senior Israeli official said Lieberman knew that talks were being held with the Egyptians, but had no idea a proposal was being finalized. Upon hearing the news, he realized that Prime Minister Benjamin Netanyahu and Defense Minister Moshe Ya’alon, who were running the talks, had left him out of the loop.
エジプトによる仲介は14日以前には全く進んでいなかったという。それが動き出したきっかけは米国のケリー国務長官が14日昼からひっきりなしに当事者たちに電話をかけ始めてからだという。ケリーがウィーンでイランと交渉しながら、次の訪問先のカイロで仲介提案をまとめようと頑張ったわけですね。しかしエジプトとイスラエルの反応が面白い。
Senior Israeli officials said that in every phone call that day, Kerry offered to fly immediately to Cairo, and perhaps even Jerusalem, to try to advance a cease-fire. But Egyptians and Israelis both politely rejected that offer, telling Kerry they are already in direct contact and didn’t need American mediation.
ケリーが「停戦仲介するよ、すぐにもカイロに駆けつけるよ、エルサレムに行ってもいい」と伝えたところ、エジプトもイスラエルも「やめてくれ」と言ったというのです。それぞれに理由があって、
Cairo objected to Kerry coming because it wanted to show that President Abdel-Fattah al-Sissi’s new government was capable of playing Egypt’s traditional diplomatic role with regard to Gaza without outside help. Jerusalem objected because it thought Kerry’s arrival would be interpreted as American pressure on Israel, and thus as an achievement for Hamas.
クーデタ以来反米民族主義で気勢を上げているエジプトのスィースィー政権は、「アメリカの助けを借りずに中東の大国としての指導力を示した」と誇りたい。イスラエル・ネタニヤフ政権は、米国から圧力がかかっている、と見られることはイスラエルの立場が悪くなっていると見られることを意味するので、ハマースを利するから嫌だ、といった話ですね。
ケリーさんはウィーンでの交渉の次にはカイロに行く、と予定されていながら結局ワシントンに戻りましたが、それはイラン核開発交渉をめぐってオバマ大統領と協議するからだけでなく、なんとイスラエルとエジプトから「来るな」と言われてしまったからなんですね。
でもケリーが圧力をかけたから結果的に停戦案の提案が早まった、とハアレツは皮肉な見方を示している。14日夜に急いで生煮えの停戦案を発表してしまったのは、ケリーがまだウィーンにいる間に出してしまいたかったからなんですね。
Ironically, however, Kerry’s pressure to fly in pushed Egypt and Israel to accelerate their own efforts to craft a cease-fire proposal.
このような手順はもともとアッバースが言い出したのだという。
A senior Israeli official said the Egyptian proposal essentially adopted the ideas raised by Abbas several days earlier. Abbas had suggested that the Egyptians first declare an end to hostilities by both sides, and then begin detailed negotiations over various issues related to Gaza, such as easing restrictions on its border crossings with both Egypt and Israel.
とにかくエジプトが停戦を宣言してしまって、その後でガザの封鎖緩和とかについて細部を話し合えばいいじゃないか、というのはアッバースから言うとハマースに主導権を握られないために好都合な手順だ。「ガザのためにアッバースが交渉をする」という形にしたいんですね。
ただ、これだと最初から最後までハマースは交渉の当事者ではないので、そもそも停戦が成り立たない。アッバースとファタハはガザを実効支配していないしハマースを統制していないのだから、いくら停戦を宣言しても意味がない。
エジプトはイスラエルに対して、ハマースを説得するよと言っていたが、実際にはハマースの政治部門にさえほとんど情報を伝えず、軍事部門にはコンタクトを取りさえしなかったという。
When a member of the Israeli team asked whether Hamas would agree to the terms of the initiative, the Egyptians tried to reassure him, saying that if Israel agreed, Hamas would have no choice but to do the same.
In reality, the opposite occurred. The Egyptians gave Hamas’ political leadership minimal information and didn’t communicate with members of its military wing at all. The internal disputes between these two wings further contributed to the confusion, and to Hamas’ feeling that Egypt was pulling a fast one.
まあエジプト政府自身がハマースを掃討作戦の対象と考えているわけだからな・・・
停戦案に大賛成なのがネタニヤフ首相とヤアロン国防相で、残りの閣僚は、とにかくエジプトが言ってるんだから受け入れるしかないんだよ、と言われて一瞬納得して賛成したので15日早朝のイスラエル政府による「停戦受け入れ」となったのだが、そもそも相手側が交渉に参加していない停戦案を受け入れても停戦は実現しない。
But a few hours later, we discovered we’d made a cease-fire agreement with ourselves.
「数時間後には、我々が我々自身と停戦合意しただけだったと気づいたのでした」というイスラエル政府高官の談でありました。
禅問答で、一つの手で拍手をしてみよ、といった命題があったと思うけれど、この停戦案はまさにそれ。手一つでは殴ることはできるけど・・・