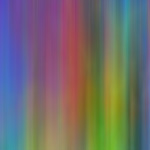駒場の東大の生協で発売されたばかりのこれを買ってきた。
『リベラルのことは嫌いでも、リベラリズムは嫌いにならないでください--井上達夫の法哲学入門』(毎日新聞出版)
「タイトルがね〜」とくさしながら読み始めたが中身がすごく真摯でかつ単刀直入なので引き込まれてしまって、タイトルなど気にならなくなった。いや、本当に、リベラリズムのことは嫌いにならないでください、と心の底から思った。
(「人文系の先生のことは嫌いでも、人文系学部は社会に必要だから嫌いにならないでくださ〜い」とか応用が効くような気もしてきた)
この著者は、私が大学に入った頃、1・2年の教養学部の頃に『共生の作法』(創文社、1986年)を読んで以来、本が出るたびに買って読んできた。
思い出深いのはやはりこれでしょうか。この本のインパクトはすごかった。
『他者への自由―公共性の哲学としてのリベラリズム』(創文社、1999年)
その当時の東大の(ある程度勉強する)学生の間では、井上達夫先生というと、とにかく圧倒的な議論のキレとそしてあの迫力(あと地底から湧いて出るような声の響きにゾクゾクします)で、ほとんど「神」扱いされていた記憶がある。実力と実績と地位が伴った本当の「権威」(あるいは好きではないが「権威主義」の源泉になりそうな人)はどの辺りかというと、私の感覚では、客観的に見て、この先生になりそうなんだが、メディアなどの扱いは必ずしも常にそうではないようだ。学問の世界での評価・相場観と、世間の認識には、ズレがある。
日本・欧米を素材とする法哲学は私にとっては直接の専門分野ではなく、正直、法律には全く興味を持てなかったので専門研究上の接点はないが、イスラーム思想を研究する際に、法哲学概念の比較を行う際にはそれなりに念頭に置いて参照した。まあ両者が離れすぎているんで比較研究とか論文に書くにはふさわしくないんだが、参照軸として有効ですね。
それよりも何よりも、啓示の律法の絶対的な優位・支配が貫徹しているイスラーム思想を、相対化するために、対置させる確固とした思想の基盤を必要としていた。私にとっては、イスラーム思想の規範に対峙してぎりぎりの共生の地点を見いだしうるのはリベラリズムしかないとやがて思い定めることになり、井上達夫先生の文章は、直接の研究のためになるというよりは、イスラーム思想と向き合う際の支えとなった覚えがある。
さて、緻密・濃厚・時にデモーニッシュに論を進めるこの先生の文章は、一般的に言ってそれほど読みやすいとは言えない。
しかしこの本はタイトルでも十分すぎるほど明らかにしているように、一般向けに、誰にでも分かるように書いてある。
第一部では憲法改正とか従軍慰安婦問題とか安保法制とか、今現在議論が沸騰している問題に、リベラリズムの思想から応えてみせる。
第二部では主要著作の要点をかいつまんで話してくれているし、思想的・学問的な歩みを振り返っているところも、単なる読者であってこの先生の「学派」には接点のない私にとっては知らなかったことが多く、興味深い。
「井上達夫思想への入門」として非常によくできていると思う。
骨格・土台においては非常に手堅く洗練された思想・理論の入門であるこの本は、しかし今現在の政治的な議論(とその混乱)への非常に良い解毒剤になっている。おそらく編集者とともになんらかの予感があったからあえてこういう体裁で出したのかもしれない。
著者はリベラリズム思想を独自に展開する過程で、一方で欧米の自由主義者、ジョン・グレイとかジョン・ロールズを批判的に継承しながら議論をしていく。他方で、日本の「リベラル派」の抱えた問題を痛烈に批判していく。
現在の政治的な議論においては、日本のリベラル派批判の部分が注目されるかもしれない。実際タイトルがそのものずばりこれなわけだし。
帯には「偽善と欺瞞とエリート主義の「リベラル」は、どうぞ嫌いになってください!井上達夫」なんて宣言してある。固い重ーい先生がすごく弾けちゃっている感じに一抹の不安があったのだが読んでみたら、上に書いたように、ちゃんとした本でした。
ウェブ上ではすでに政治的な議論についての要点が紹介されていた。自衛隊と安保条約の憲法問題について、日本のリベラル派の主要な立場を「修正主義的護憲派」と「原理主義的護憲派」に分け、それぞれの矛盾と欺瞞をつく。
修正主義的護憲派は「新しい解釈改憲から古い解釈改憲を守ったにすぎない」として、解釈改憲に反対しているという主張を「ウソ」だと突き放す(49頁)。
他方で原理主義的護憲派は「自衛隊と安保が提供してくれる防衛利益を享受しながら、その正当性を認知しない。認知しないから、その利益の享受を正当化する責任も果たさない」のであって、これは「許されない欺瞞」であるという(50頁)。
池田信夫さんの引用していない部分にはもっとすごい炸裂トークがある。例えば日本での典型的な「リベラル派」とされるこの原理主義的護憲派の近年の堕落が著者には感覚的にかつ論理的に許し難いようで、「最近の原理主義的護憲派の論客の中には、こうした欺瞞をあっけらかーんと認めて、それが大人の知恵だ、みたいなことを言う人がいる」と実名・著作を挙げて批判。何が問題かというと、「要するに、原理主義的に護憲を世間に主張しながら、実際には自衛隊と安保を認めていることを、みずから世間にバラしている。護憲批判派が読みうる公刊された本の中で。他者の批判的視線を無視した「お仲間トーク」というのか、この神経がわからない」(51頁)
そういう行為は「いわば、通勤電車のなかでお化粧にはげむ若い女性と同じですね。その女性にとって、ほかの乗客の視線は無きにひとしく、ただのモノでしかない。こういう原理主義的護憲派にとって、彼らに批判的な人々の存在など無きにひとしく、ただのモノだと思っている。相互批判的な対話のパートナーとして認知していない」(51頁)
・・・と電車で見かけた女性も巻き込んで怒りの対象にしておられます。「還暦すぎたからといって円くなっていられない。「怒りの法哲学者」として、角を立てて生きていきますよ」(195頁)だそうですので。
井上先生にとっては何よりも、日本の「リベラル派」の言動における公共性の欠如が許し難いのでしょう。
日本のリベラル派の底浅い党派的言動への怒りと、欧米のリベラリズム思想への理論的な批判は、次元と場面を異にしているけれども、どこか通じるところがある。例えばグレイが「不寛容への寛容」を認めてしまいリベラリズムの普遍性の主張をあからさまに取り下げることや、ロールズが立憲民主主義の伝統を持たない社会へのリベラルな正義原理の適用を諦め、不平等や独裁すら一定の「節度」のもとで黙認する姿勢に、著者は失望する。これらは「寛容」の負の側面であるとする。「寛容」を主張することで往往にしてその背後で放棄される「啓蒙」の側面を著者は再度重視する。もちろん「啓蒙」には負の側面もある。しかし日本には「啓蒙」がその肯定面でまだまだ必要であるというのが著者の立場だろう。
1980年代末から90年代初頭にかけて、昭和天皇崩御から冷戦崩壊の時期に、著者は気づかされた。「保守派が言う「伝統」も含めて、戦後日本のなかに、リベラリズムの足場になるようなものが実はなかった。その怖さを実感しました。ショックでした」(106頁)
「リベラリズムは、啓蒙と寛容という二つの伝統から生まれたと言いました。
しかし、啓蒙にも寛容にも、これまで言ったように、ボジとネガがある。
両者のネガを切除し、そのポジどうしを統合させるための規範的理念が、私が考える正義なんです」(20頁)
20〜30頁あたりで、著者の正義論の骨子が、これまでになく平易に語られています。
その上で国家・国旗問題や従軍慰安婦問題、アメリカやドイツの歴史認識や「謝罪」と日本との比較、そして集団的自衛権など、政治問題といった具体的な課題に著者のリベラリズム思想を応用していく。
集団的自衛権については著者は反対だが、「なんらかの集団的な安全保障ネットワークは必要です」という。国際政治学者や安全保障研究者ではないので、具体的にどうすれば、という話にはならない。昨年の安倍内閣の集団的自衛権行使容認の閣議決定によって、アメリカに対する交渉カードを政府が自分から捨ててしまった、と批判し、「安倍政権は、日本の国益と政治的主体性を本当に守ろうとしているのですか」と問いかける。違憲論ではなく戦略的に主体性がなく、戦術的に稚拙と批判するのですね。
そして日本の「リベラル派」の枠を打ち破るのが、憲法9条削除論です。
「九条解釈としては、文理の制約上、絶対平和主義を唱えているとしか、捉えようがない」(46頁)ことから、先ほどの「修正主義的護憲派」や「原理主義的護憲派」のような、嘘や欺瞞を抱え込まざるを得ない。そのため、「私は、憲法九条を削除せよ、と主張しています」(52頁)と言い切る。
「私は、安全保障の問題は、通常の政策として、民主的プロセスの中で討議されるべきだと考える。ある特定の安全保障観を憲法に固定化すべきではない、と。だから「削除」と言っている」(52頁)
この本で繰り返し出てきますが、九条があることで「リベラル派」が抱え込む欺瞞と、その状態に安住できさえすることによって極まる知的堕落が、著者にとって我慢ならないようです(正義論の法哲学者はこうでなければなりません)。
「だから私は、安倍政権の姿勢を批判する論理的および倫理的資格が、護憲派にあるかというと、ないと今思っています。解釈改憲OKの修正主義的護憲派にも、違憲事態固定化OKの原理主義的護憲派にも、そんな資格はない」「これ以上、立憲主義をコケにすべきでないと考える点で、護憲派とは違う」(54-55頁)
天皇制についての提言にも共通しますが、この著者はいくつか、いかにも思想・理論家の学者が言い出しそうな、政策論としての実現可能性はきわめて低いが論理的には筋が通った解決策を提示します。具体的な政策としてというよりも、何が政策の目的であるか、実現されるべき価値であるかという面で、深く受け止める価値があるでしょう。
もし著者のような筋道で社会の多くの人が考えるようになれば、議論はもっとずっとまともになるでしょうし、その結果としての選択もましなものになるでしょう。時に重苦しく感じられる普段の著者の文章は、そのような根本的な楽観主義に貫かれているが故に、慣れると極めて心地よい読書体験となるのです。今回の本は、苦行の部分を飛ばしていきなりハイになれるようなそんな本です(著者も?)。
「学者の言うことを聞け」というのは、都合のいい時だけ都合のいい「権威」を祭り上げて付和雷同を誘い、異論を権威主義で黙らせるといったことではないのです。根本的に、広く深く考え抜いた数少ない知性による、時に突飛にも見える問いかけを十分に聞き取り、そこから社会が民主的制度の中で判断していくということだと思います。そのために学者は一日二十四時間、頭が割れるほど考えていてくれるのですから。