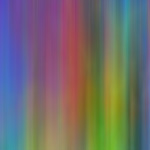この時期、月刊誌が送られてきます。研究室に来てみると『文藝春秋』と『中央公論』などが届いていました。
こういう雑誌の慣行として、寄稿していると送っていただけるようになります。私は親の代からそういう生活をしているので、執筆することもある月刊誌が定期的に届くとさっと目を通す、という生活に慣れ親しんでおります。
送られてこなかったら買って読むかというとそれは全く別の問題なので、通常の意味での正式な読者ではありませんが、雑誌の紙面が自分の「仕事場」「市場」ともいえるので、そういう目で、半ば「自分のこと」として、子細に、またシビアに見ているという意味で、通常より熱心な読者と言えます。
寄稿したことがある人は大学業界などの書き手や、あるいは政治家・経営者・官僚などの実務家を中心に、累計ではかなり多いので、送られてきている人も多いでしょう。こういった月刊誌の一定の割合の部数は「書くこともある」層に届けられており、それによって大学業界人や実務家の間での「世論」「共通認識」を形成する土台になっているのかもしれません。
(なお私の父は自宅を郵便物の宛先にしていたので、小さいころから私がそれを読んでいたわけです。そのため、団塊世代が「若造」に感じられる60年安保世代的な世代感覚が身についてしまいました。文藝春秋の読み手・書き手の中心的世代が「60年安保」世代であることは、芥川賞150回記念のアンケートで「柴田翔」に数多くの言及がなされたところから明らかでしょう)
しかしねえ、『中央公論』の表紙にもお題が掲げられたカバーストーリー(目玉特集)は「生き残る大学教授」・・・
あのねえ、対象となる読者層が限定されすぎていませんか?とさすがに言いたくなるよ。無料で送ってもらっている執筆者の人たちしか実感を持って読めないぞ、この企画?
業界関係者としては絶対に言ってしまってはいけない、、、と思いつつおそらくこれを読んだ業界関係者の多くが頭の中であるフレーズを思い浮かべていると思うのでそういう時にはつい癖というか過剰な役割意識で言ってしまうのだが「生き残れるのか中央公論」
ああ言ってしまった。
内容は、ライター的な人が書いている「覆面座談会」「大学教授の生活ぶっちゃけ話」を見ても、大学関係者が普段ぶつぶつ言っていそうなことが断片的にそのまま露出している、「まあ間違ってはいない」というような話である。世の中に出回る「大学教授」への妄想や誤解をそれなりに矯正する効果はあるかもしれないが、どれだけ公共性・公益性があるか分からない。
子供のころから親も祖父も親戚にも大学教授が多く、当然その親・親戚の友人・知人にも大学教授が多かったので、疎遠な人も含めて「ここで描かれるこの人はあの人みたいなタイプだな」と実例が思い浮かぶ場合もある。あまり当たっていないなあと思うところもある、単に私の周りの大学教授が大学教授の中でも特殊なせいかもしれないが、などと考えて読んだという意味では楽しめたが、さてこれが総合雑誌の特集として適切なのか、というと疑問だ。
大学の仕組みや大学教授と呼ばれる人たちのありがちなひどい行状から、「私だってこうも言ってしまいたくなるよ」というようなある程度共感できる内容とはいえ、それが実際に総合雑誌に今月の目玉特集として載ってしまうと、やはり「こんなこと載せる必要があるのか?」と言いたくなる。読み手としてだけでなく書き手としての立場からも。
ここで関連が気になるのが、最近の、一定の質を保っている月刊誌に多い、大学の広告。『中央公論』の今号では、「特別企画」の慶應義塾塾長のインタビュー(広告)を含めた各大学の広告が144-167頁に電話帳みたいに延々と載っている。大学にとっては、扇動・排外意識むき出しだったり、おちゃらけエロ満載だったりするあまり品の良くない媒体に広告は出したくない。逆に、雑誌を出す方から言っても、誌面の品位を落とさないで済むような世間体の良い広告主を切実に求めている。『中央公論』は、「大学広告」に関しては、広告媒体と広告主との関係の相性がいいのだろう。
だとすると「大学教授」特集は広告スポンサー向けなの?そうだとするとつじつまは合うが、いっそう公益性がなくなるんじゃないの?
まあ『中央公論』がいろいろ苦しいのは承知の上でこれを書いている。『中央公論』の存在は得難いので頑張っていってほしいと思っている。このなにやら?な特集にしてもその枠があるから、竹内洋先生のいつものもっともらしい茶化し芸(「大学教授の下流化」)や、上山隆大先生の力の入った米大学産業論も読めたわけだし、
なお、浜田東大総長のインタビューで、いつものことながらあげられるのが「インド哲学」。
「たとえば、最も現場に遠いと思われがちなインド哲学を例にとっても、仏教界、要するに寺はその「現場」である。分野にもよるが、これからの時代、教員は、そうしたそれぞれの「現場」との結びつきをさらに意識する必要があるだろう」
と語っておられますが・・・一応世間の誤解を修正しているようにも見えますが、本当に分かっているのか不安。
「大学改革=自分で金稼いで来い、産業界に役に立つものにしろ、いやそれはいかがなものか」系の議論が勃発するたびに、いい意味でも悪い意味でも「役に立たない」「金儲けできない」学問の例として「インド哲学」が挙げられる。しかし、これは最初から最後まで認識不足。
「インド哲学(正式にはインド哲学仏教学科)」は簡単に言うと「サンスクリットを読むところ」です。
なんでサンスクリットを読むかというと仏典は元々はサンスクリットで書かれているからですよね?法事でやってくるお坊さんの大部分は漢訳当て字のお経を棒読みしているだけでしょうが、格式の高い寺や、大きな宗派の総本山では研究所とかもあってサンスクリットから読める人を確保しておかないと格好つきませんよね。
ですから昔から、名のある寺は、息子を東大に通わせてサンスクリットを読めるようにさせたのです。まあ東大だと他の思想や文化や科学に触れるので素直な跡継ぎにはならなかったかもしれませんが、問題はそんな狭いものではない。
寺というのは、個々の身近なところを見れば、勉強しないし堕落しているし金儲けばっかりしているし、と見えるのかもしれませんが、総体で見ると、かなり人材を囲い込んでいて資金があって、有効にかどうかわかりませんが、それを使って大きなことをしています。
京都に行ってみなさい。東京とは全く違う経済・産業があります。新聞各紙は「寺番」記者を張り付けています。東京では霞が関の官庁回りをしますが、京都では「寺回り」をするのです。それは「文化面」だけではなく経済・政治の欄に書くべき出来事が、寺を媒介して起こっているからです。
東京にだけいると、実際には日本社会で力を持っているこの方面の経済力や政治力に気づかないので議論が変になるのです。
サンスクリットで仏典の研究を、となると、学部の2年間の専門課程程度で終わる話ではないから、中心は大学院教育になる。一般の学生から言えば、日本では学部出てすぐ就職しないといけないという強迫観念があるから「論外」の学科に見えるかもしれないが、寺の子供からいうとすぐに寺を継ぐわけではないから時間はたっぷりある。別の学科を出てから、あるいは一度ビジネス界に入ってからの学士入学・大学院進学も多くなる。
筋の良い寺の子供は、寺を継ぐ前に外国留学したりビジネス経験を積んだり、それぞれの寺とその家の家風によって固有の育ち方があり、時代に合わせて各世代が育って、それによって寺は変わってきて、経営体としても刷新されてきたんです。出来の良い子なら、自分の寺の経営体としての規模や資産は小さいころから自然に呑み込んでいるし、適度に新機軸を打ち出していかないと自分も面白くないしなにより寺として生き残れないことは分かっている。
その際に「インド哲学科」もそれなりの役割を果たしてきた。いわば大昔から産学連携を「産」主導でやってきたの。それを東大内部で管理職になるような人たちが、世間一般と同様に知らなかったのは、それはまずいでしょう。
東大の大部分の学部生にとってインド哲学は「何をやっているところか分からない」ということになるでしょうし、「就職なさそう」ということになるのでしょう。しかしそれは衆生の無知、ということに過ぎない。それは大学・学部入学までにマス教育で詰め込まれた「偏差値」(あと東大では3年進学時の「進学振り分け」)的な基準で推し量った、子供の軽率な判断にすぎません。大部分の一般学生がそのような尺度で物事を見ている、ということは、それが真実であるということを意味しません。例えば大きな寺の子、有形無形の資産を豊富に抱えて今後それをどう活用していこうかと考える寺の子は全く違う目で見ているわけです。で、後者の方がもちろん正しい。
問題は、受験にもまれて辛うじて東大の難関を突破しただけでは、その後大人になっても認識を改める機会がないこと。日本社会や経済における仏教界の力やヘゲモニーに気づく経験がないままに齢を重ねて、その中の一部がエラいさんになって、学生時代のぼんやりとした思い出から「インド哲学は儲からない、就職先がない」的な誤解を持ったままで議論しても話は進みませんよね。
もちろん、東大が、本当の意味で仏教界に関わっている良質な人材の持つエネルギーを取り込んでいくような魅力や発想を持っているか、十分に取り込んでこれたか、適切な制度を持っているかは別問題で、そこには大いに改善の余地があると思いますよ。
でも制度を整えないと人が来ない、というのも間違いじゃないかと思います。
私は学部・学科選びの時、「イスラム学科」というできたばかりの学科を発見して、これは、今後文章を書いていくのにまたとないものすごくビジネス・チャンスのある学科、と狂喜乱舞しましたが、イスラム学科がそのようなことを謳っていたわけではありませんし、制度としても実態としても、学科の先生とおんなじ分野を研究する、という発想の学生以外に対しては、何らケアはされておらず放任でした。でも東大というものすごく恵まれた条件のもとで、「モノ書きの素材とするには何があるか」という観点から、本郷の化学の先生が出張で教養学部に教えに来ていた「フリーズ・ドライの作り方」(直接役立っていないがコンビニで最新のカップラーメンを見るのが楽しい)から、現代英米政治思想(これは今も直接役立っている)まで、提供されている授業をつまみ食いした結果、「イスラム学!ここここれは使える」と確信して進学したわけです。思想でも文学でもきちんとイスラム学をやった上で発言している人は一人もいなかったから、という極めて合理的な選択です。学科そのものがなかったんですから当然ですが。小林秀雄の時代はフランス文学があらゆる意味で最先端だったんですが、当然現代はフランス文学は完全に出来上がってしまった分野でそこから新しい価値を生み出していくのは容易ではありません。それに対して出来立ての学科、これまで誰もやっていなかった分野の知見を身につければ競争力がつくのはごく自然に予想できることです。もちろんイスラム学単独では使いにくいので、思想・文学方面とつなげたり、実際に現地で起こっている紛争や政治運動や国際関係を研究対象に取り込んだり、政治学や社会学の知見を応用したり、といったことを考えて東大内のあらゆる学部学科・施設を利用しましたので、学費のモトは十二分に取りました。社会情報研究所(当時)の研修生課程なんていう、東大の学生なら授業料タダというすごいいい話ににも乗って試験受けて入ってメディア論や中東政治・メディア政治(こんなところに中東に詳しい政治学の先生がいたんです!)を勉強しつつ最長の年限(4年間)居座ってコピーセンターとして利用させていただいておりました。ありがとうございました。その後コピーの枚数が制限されたみたいなことを聞いたが関係ないかな。
お仕着せのカリキュラムではなくカスタム・メイドで自分の専門分野を構築できたことが、私にとっては東大に入ったことの最大の利点でした。東大、特に文学部はそういうカスタム・メイドの要素を残す、あるいは一層強めていくことが重要なんじゃないかと思います。私のやり方はその時のその瞬間で最適と思ったものを選び取っただけで、今現在学生の人には別の選択・組み合わせが当然あるはずです。
話を戻すと、インド哲学というのは、本来は仏教界方面に最終的な就職先が決まっている人が来ればいい、「一見さんお断り」と言ってしまっていいぐらいの左団扇な分野なわけです。国立大学だからそんなことを公言しないですし、もちろん教員は仏教関係の出身じゃなくてもなっていますけどね。(インド哲学仏教学科の今の人たちとは全くつながりがないので、あくまでも長い歴史の中での趨勢の話をしております)。
もし「国は今後インド哲学にはお金を出さないから、産業界から資金を募れ」ということになっってしまったら、一瞬にして仏教界からお金が集まるでしょう。どこの宗派が主導権を握るか、新興宗教系の教団も加われるのか、といった点で争いが勃発するかもしれませんが(怖い)、お金が集まらないということはあり得ません。(実際、宗教学科関係のプロジェクトには、新興宗教方面からすでに潤沢にお金が入ってきていますし・・・)
本当の問題は、そうやって産業界(ここでは仏教界)あるいは特定の寺に資金を出させたら客観・中立な研究はできないでしょ、ということであって、だから結局は細々とながら国が出す、ということになるしかないのは最初から分かっている話です。思想・宗教といった文学部の諸学は、「価値」という究極的にものすごいパワーを秘めたものを扱う分野ですから、スポンサーをつけるとややこしくなるのは当然です。
大学を改革せねばならん、と言う人は、まず大学を知ってほしいものです。改革の議論は、まず論者自身が大学を知るきっかけになる、という意味では結構なことです。その上でいい知恵も出るかもしれません。大学関係者にとっても、改革議論に応えていくうちに、自分たちもあまり知らなかった・重視していなかった大学の価値を再発見することにもなります。
・・・なんてことを書いていたら、今号の第二特集「中露の膨張主義──帝国主義の再来か」に触れる時間が無くなってしまった。本当はこっちの方が重要なんだけど。 このブログでもちょっと触れたように、『フォーリン・アフェアーズ』の5/6月号でのウォルター・ラッセル・ミードとジョン・アイケンベリーの論争は、現在の国際政治をどう見るか、今後どのような政策を採用していくべきか、という課題についての対照的な見方や論争の軸を提供しているが、それに呼応して敷衍したものと言える。アイケンベリー本人にもインタビューしている。 一方で「中・露・イランなど現状変更勢力・地域大国の台頭、地政学的論理の上昇」というミード的な見方が盛んになされており、そこに刺激を受け、日本の政策としては「地政学的観点からもっとロシア・プーチンに接近しろ、没落するアメリカは当てにならない」系の議論が右派を中心に民族主義系の左派からも提示される。 それに対してなおも「1945年以来の米中心のリベラル多国間主義は優勢だ」というアイケンベリーの議論が応戦していて、オバマ政権としても正面からの理論武装はこちらを踏まえている。そこからは日本は米国との同盟強化で乗り切れ、という話になって日本のメインストリームはこの路線だろう。『リベラルな秩序か帝国か アメリカと世界政治の行方』(上下巻、勁草書房、2012年)で示された枠組みですね。 このような大体の枠組みを踏まえたうえで、中西寛先生の重厚な総論、渡部恒雄・川島真・細谷雄一諸先生方による鼎談を読んでいくと、フォーリン・アフェアーズとはまた違う、日本ならではの歴史・思想や地域研究を重視した視点が得られる。日本語を読めてよかったと思える瞬間です。 こういう有益な特集をやるために、カバー・ストーリーは「生き残る大学教授」特集で広く一般読者を惹き寄せ・・・というのならいいんですが問題はそれで読者が釣れているように見えないことなんですけどねえ。私は釣られましたが、業界関係者ですから統計的な数に入りません。