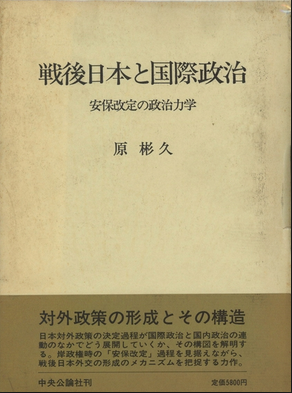ここのところずっとこの本からの抜き書きをしているのだが、


今日は一休みして回り道。
この本は、私は学生時代に読んだはずなんだけれども、こんなに読みやすかった印象がない。私の方で何かが変わったのか、世の中が変わってリアリズムがより受け入れやすくなったのか。
2013年に文庫化されて、手軽に安価に手に取れるようになったというのがかなり大きい要因かもしれない。単行本はとにかくでかくて重くて活字も古くていかにも古色蒼然とした本に見えた。ところが文庫になると肩に力を入れずに読める。
あと、原彬久先生の訳文が読みやすい。この本は元々は1986年に福村出版から刊行されたもので、「現代平和研究会」による共訳で、代表者が原先生ということになっている。各章の翻訳担当者は各巻の冒頭に記されているが、私などは名前だけしか知らない上の世代の、いずれも錚々たる学者である。
文庫版では原先生が監訳者となっている。翻訳代表者・監訳者がどれだけ全体の訳文に手を入れて統一させたかは、かなりよく調べてみないとわからないが、全般に読みやすいものになっていると思う。ここまでのところは総論・序論である第一部から引用してきたが、監訳者の原先生の担当部分であった。そういえば、E・H・カーの『危機の二十年』は以前から岩波文庫に入っていたけれども、読みにくかった。この本を2011年の新訳ですごく読みやすくしてくださったのも原彬久先生だった。


『危機の二十年――理想と現実』(岩波文庫)
単に訳文が読みやすくなっただけでなく、カーの新訳が出た頃から、国際政治、特にリアリズムの古典について、それを読むわれわれの側で何かが変わったような気がする。翻訳者も訳しやすくなったということかもしれない。
そんなことを考えながら原先生の著作をアマゾンで見ていたら(個人的に面識はありません。一度何かの会合で同じ大きな部屋にいたことがあるぐらいでしょうか)、なんだかどれも今読むと面白いんじゃないか?というタイトルだ(以前に読んでも面白かったですすみません)。中東とはまったく関係ないんだが、日本の今夏の政治・思想状況を思い起こすと、涼しくなった秋に頭を冷やして読み直したほうがよさそうだ。
まず、最近出た、オーラル・ヒストリーの総まとめ的な本から。


『戦後政治の証言者たち――オーラル・ヒストリーを往く』
で、いったいどういう対象にオーラル・ヒストリー聞き取りを行ってきたかというと、一方で岸信介。


『岸信介証言録』 (中公文庫)
上記はオーラル・ヒストリーの原資料的なもの(もちろんある程度編集してあるが)だけれども、それに基づいた成果はもっと以前に刊行されている。
それがこれ。


『岸信介―権勢の政治家』 (岩波新書)
これが出た時は、このテーマはまったく違う政治的位相の元で読まれていた気がする。
遡っていきましょう。これ。これも昔読んだと思うけど、今読めばまったく違う印象だろう。


『日米関係の構図―安保改定を検証する (NHKブックス)
そして60年安保の結果として固定化された日本政治の構図の中で、岸の対極に位置して存在してきた野党=社会党的なるものも同時に研究対象になっている。
あの「記念受験」かつ「同窓会」的な発想のデモと国会審議を見てしまうと、社会党的なるものは今こそ客観視できるような気がする。そうなるとこれ、今絶対読みたい。締め切り抱えているから今読めませんが。


『戦後史のなかの日本社会党―その理想主義とは何であったのか』(中公新書)
岸信介を岩波新書で、社会党を中公新書で、というクロスオーバーのバランス感覚が絶妙でたまらんですな。こういうところが日本の出版文化の妙だったんですが、硬直党派化・短期商売窮乏化して貧して鈍して失われかけているものでもあります。
こうなるとまったく専門に関係ないから読んでいなかったこの本も、現代日本への興味から読んでみたくなる。取り寄せてみよう。モーゲンソー『国際政治』、カー『危機の20年』の翻訳と60年安保の政治学とのつながりが見えてきますね。
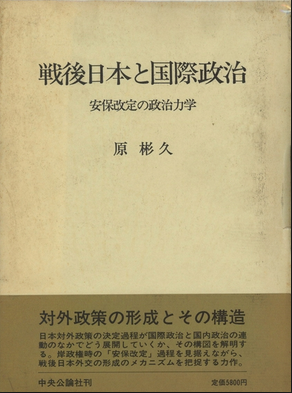
原彬久『戦後日本と国際政治―安保改定の政治力学』中央公論社、1988年
学者の仕事って、何十年も経ってから読まれる本を何冊書けるかが勝負なので、そういうテーマに当たるか、その時間と環境があるか、考えれば1分も無駄にはできない。
「息の長い」って言葉も考えてみれば怖い言葉で、すごい時間がたっても無知無理解・暴論が飛び交っていても、とにかく生き延びて、「死んでない、息してる」ってことが重要だということだからね。
私は息も絶え絶えです。