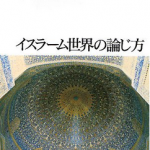『現代アラブの社会思想ーー終末論とイスラーム主義』の第9刷が、先月から市場に出ています。
Kindle版も出ていました。
9刷の部数は2100部、と細かい。新しい帯が付いています。
累計は5万6100部になりました。
2002年の1月に刊行されてから13年間、よく長く生き続けてきました。長く生き続けるということこそが、評価の一つと思っています。
この本は、自分自身の研究者としての歩みを振り返る時に、忘れることのできない本です。
なによりも、あの時点でしか書けない本でした。
あらゆる研究者は、最初の研究で、最もオリジナルなものを出さねばなりません。世界中でまだ誰も言っていないことを言わないといけないのです。
しかしなかなかそれはできません。思想史であれば、大抵の影響力のある思想テキストは全て隅々まで読み尽くされ、論文の対象にされ尽くしているからです。
私の学部から大学院にかけてのエジプトでの資料収集で、いくつかのテーマと資料群が浮かび上がりましたが、その中で言及することが最も厄介で、かつ先行研究がない対象が、アラブ世界に広がる、膨大な終末論文献でした。
この本の後半部分を構成し、最もオリジナルな部分は、2001年11月に刊行されていた論文「前兆・陰謀・オカルト──現代エジプト終末論文献の三要素」末木文美士・中島隆博編『非・西欧の視座』(宝積比較宗教・文化叢書8、大明堂、2001年、96-120頁)からなります。
宗教学・思想史の固い叢書に、全く新しい、つまり評価の定まっていないテーマと資料についての、全く無名の著者による論文の収録を認めてくださった編者の先生にはひたすら感謝しておりますが、それを新書という一般書の枠に収めるというものすごく無茶な構想を受け入れた、当時の講談社現代新書の編集者の大胆さも、今振り返ると、傑出したものでした。
そして、2002年1月という時期に出せたことが、何よりも今となってはかけがえのないことです。時間を巻き戻すことはできません。今なら、もっと完成度の高い、整った形で書けるかもしれませんが、それを2002年に戻って出すことはできません。
研究者は生まれてくる時代を選ぶことはできません。
自分が大学院にいる間に現れてきた、まだ他の研究者が触れていない対象に、誰よりも早く手をつけて成果を出さなければならないのです。
中東と、あるいは学術の世界をリードする欧米と、言語や情報のギャップのある日本の研究者として、中東の思想や政治をめぐって誰よりも早く新しいテーマに取り組んで成果を出すことは、至難の技です。
その中で、この本とその元になった論文は、結果として、欧米でこの文献群を用いたまとまった研究が出るのに先んじて発表した形になりました。
その後数年すると、現代の終末論文献を扱って学界に名乗りを上げる若手研究者が、米国でもフランスでも現れてきました。あと数年ぼやぼやしていたら、私の本は「後追い」になってしまったでしょう。
でも当時は日本では「後追い」が普通で、むしろ、全く欧米の先行研究がないものをやると、評価されなかったりしたのです・・・「欧米の権威」がやっていることを輸入するというのが主要な仕事だったのですから。
その後、このテーマは結果的に「欧米の権威」が扱うものとなりました。一つ目はこれ。
David Cook, Contemporary Muslim Apocalyptic Literature, Syracuse University Press, 2005.
Kindleでもあるようです(David Cook, Contemporary Muslim Apocalyptic Literature (Religion and Politics))。
クックさんは短い論文の形では、私より早く現代の終末論文献の存在に着目していたようです。しかしまず古典の終末論について本を出してから、現代の終末論文献に本格的に取り組みました。
古典終末論について書いたのはこの本です。
David Cook, Studies in Muslim Apocalyptic, The Darwin Press, 2002.
クックさんは私と同年代ですが、その後、 米テキサス州のライス大学の准教授になりました。そして、終末論についての研究を一通り発表したのち、ジハードの思想史に取り組んでいます。
David Cook, Understanding Jihad, University of California Press, 2005.
紙版は増補版(Understanding Jihad)が出版される予定のようですが、Kindleでは初版が買えます。研究上は初版が重要です。もちろん、その後の「イスラーム国」に至るジハードの拡大をどう増補版でとらえているか、クックさんの研究がどう進んでいるかにも大いに興味がありますが。
「終末論からジハードへ」という研究対象の変遷は、イスラーム政治思想の内在的構造化が、必然的な道行きと思います。
フランスでも同じ素材で研究が出ました。
Jean-Pierre Filiu, L’apocalypse dans l’Islam, Fayard, 2008.
英訳はこれです。
Jean-Pierre Filiu, tr. by M. B. DeBevoise, Apocalypse in Islam, University of California Press, 2011.
フィリウさんはパリ政治学院で学位を取って母校で教鞭を執っている人です。この著者は研究者になったのは私より遅いのですが、年齢はひと回り上(1961年生まれ)で、まず外交官として中東に関わったとのことです。
私は、フィリウさんが外交官をやめて大学院生になったかならないかぐらいに、のちに彼の指導教官となるジル・ケペル教授に会いに行く機会がありました。その際に出たばかりの私の『現代アラブの社会思想』を見せて、日本語なのでケペル教授は当然読めませんが、資料の写真を多く入れておいたのと文献リストを詳細につけていたことで、扱った文献について話が盛り上がりました。
ケペル教授もこの文献群の存在は認識しており、この文献を扱った本を出したことについては、けっこう驚いているようでした。後に、自分のところに来た学生がこの文献群をテーマとして選ぶ際に、微妙に影響を与えたかもしれません。といってもフィリウさんは私よりずっと以前から中東に関わっているので、とっくにこの文献群の存在と影響には着目していたでしょう。
その後フィリウさんは活発に中東論者・分析家として活躍しています。
私について言えば、この本を書いたのは、日本貿易振興会アジア経済研究所の研究員になって1年目の年でした。終身雇用のアカデミックな研究所に就職して、普通なら放心してだれてしまうところでしたが、就職して半年で9・11事件に遭遇し、中東の激動が始まるわさわさとした予感の中で、衝き動かされたように書きました。
クックさんやフィリウさんのような学者が研究を完成させる前に、このテーマについて論文と本を出しておけたことは、今振り返ると、当時の自分を褒めてあげたい気持ちになります。当時は他国の研究者との競争など考えず、ただ無我夢中に論文や著書刊行の機会を求めて、与えられた機会に必死に出しただけだったのですが。
また、この本が広く知られるための後押しとなったのが、この年の暮れに大佛次郎論壇賞を受けたことでした。
どなたかが候補作にあげてくださったのですが、それを審査委員の一人、米国で長く研究をしてきたある先生が、強く推してくださったことで、一気に流れが決まったという裏話を聞きました。どうやらかなりの番狂わせであったような雰囲気でした・・・
当時は「研究員」という立場で賞をもらうことはまずないというのが、日本の言論界の暗黙の前提でした。当時の日本は今よりずっと不自由で、序列を気にするガチガチの社会だったのですね。
また、端正でリベラルな学究の先生が、このような野蛮なテーマを扱った破天荒な学術研究を一番に推してくださったという話も、一般的な印象とは合わないかと思います。
しかしかなり経ってから米国の学術界や社会一般との接点ができるようになったころに気づいたことは、その先生は、この本の出来がいいからとか、完成されているからといった理由でこの本を推したのではないだろう、ということです。
そうではなく、一番変わった説を打ち出している、一番若い人の候補作に、米国での当然の作法として、機会を与えるという意味で賞を与えただけなのでしょう。
米国の社会は、何か人と違うことを考えている人が、一歩前に踏み出して発言しようとした時に、その機会を与えてくれる社会です。何かをやってやるぞという若い人に、まず一回は機会を与える。それが自然に行われています。
機会を与えられて発言を許されたということは、それだけでは何も意味しないのです。その発言が意味のあるものか、社会に何か違いを与えられるか、その後の活動で真価を証明して初めて、その人と作品は評価を得られる。
機会を与えられたということだけでは、評価されたということを意味しないのです。
このあたりは、「発言」があらかじめ「立場」によって決まっており、その評価も立場の上下をもってあらかじめ決まっていかのような前提を抱いている人が多い日本では、あまり理解されていないことかもしれません。そのような前提の下では、発言の機会を確保しているということ自体がなんらかの「上」の立場であることを意味し、すなわち内容の評価を意味するという、強固な観念が生まれます。
米国の社会にも、その社会が生む国際政治の政策にも、悪いところはいくらでもあるでしょう。しかし、「若い人が新しいことをやろうとしているときに、一回は機会を与える」という米国の社会の根っこに強固に定着した原則は、素晴らしいものだと思いますし、それが米国の活力や競争力の源であると思っています。
そのような米国的な発想により、大量の出版物の渦の中で押し流され消えそうになっていたこの本が、拾い上げられ、翼に風を送られたかのように再び浮上したことは、奇跡的であったと思います。この本が今後も飛び続けられるように、私がたゆまず風を送り続けることが、機会を与えてくださった先生に応えることになるのだと思っています。