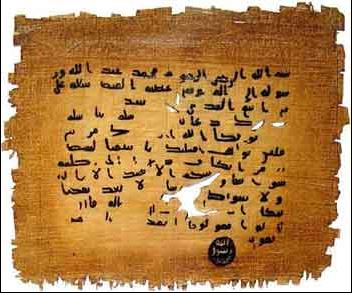『週刊エコノミスト』に連載の読書日記、第5回が発売になりました。
池内恵「帰省して「封建遺制」を超えた祖父の書棚へ」『週刊エコノミスト』10月7日号(9月29日発売)、67頁

今回はちょっと私的なことを書いてみました。紀行文風ですが、実際には今後ゆっくり書いていきたいことの種を方々に仕込んであります。かつての日本の学問と「養子」という制度の関係とか、明示的ではないのだけれども、私的なところを出発点に、地下茎のように伸ばしていきたいテーマがあります。直接的には9月の連休に、祖母のいる金沢に久しぶりに帰った際に見たものや読んだものを扱っているのですが、本当はいくつかの発展させたいテーマについての布石です。
『週刊エコノミスト』の「読書日記」欄は、連載と言っても5人の執筆者が順に担当するので、5号に1回廻ってくる私の回を続き物として認識している人は、このブログを丹念に読んでくれている人だけだろう。
5回目になって、どうやら節目のようなので、この連載(私の回だけの「続き物」としての)で何をやろうとしているのか、改めて書いてみよう。
本人の意識としては、壮大なパズルの小さな小さなピースを一個ずつ、各所に置き始めた段階なので、自分以外には全体像は見えないと思う。
まずこれまでの連載を列挙して振り返ってみたい。ブログで毎回告知してきたので、エントリへのリンクを付しておこう。
(-1)読書日記の連載を始めます(週刊『エコノミスト』)
4月1日に、今年度の決意のような形で、この連載の趣旨を書いておいた。多くはここですでに書いてある。連載が始まる前に、カウントダウンのように2回予告のエントリがある。
4月1日のエントリでは、書評(あるいは読書日記)という、日本の新聞・雑誌に確立した様式・制度から、非常に逸脱したものを意図していることを記してある。
以下要点を《 》内に再録してみよう。
まず、「書評はもうやりたくない」と書いてある。
《『書物の運命』に収録した一連の書評を書いた後は、書評からは基本的には遠ざかっていた。たまに単発で書評の依頼が来て書くこともあったけれども、積極的にはやる気が起きず、お断りすることもあった。たしか書評の連載のご依頼を熱心にいただいたこともあったと思うが、丁寧に、強くお断りした。》
その理由はいろいろ書いておいたが、一番の理由はこれ。
《新書レーベルが乱立して内容の薄い本が乱造され、「本はタイトルが9割」と言わんばかりの編集がまかりとおる出版界の、新刊本の売れ行きを助けるための新聞・雑誌書評というシステムの片棒を担ぐのは労力の無駄と感じることも多かった。なので、書評は基本的にやらない、という姿勢できた。》
それでは何故今回やる気になったかというと、次のような条件を出してもなお編集部が呑んでくれたからです。
《「新刊本を取り上げるとは限らない。その時々の状況の中で読む意義が出てきた過去の本を取り上げることも読書日記の主要な課題とする。さらに、読書日記であるからには、外国語のものや、インターネット上で無料で読めるシンクタンクのレポートやブログのような媒体の方を実際には多く読んでいるのだから、それらも含めて書く。その上でなお読む価値のあるものが、日本語の、書店で売られている、あるいはインターネット書店で買うことができる書物の中にあるかどうか検討して、あれば取り上げる」。》
これは、日本の出版慣行・制度から見ると、とんでもないことを言っています。
まず「新刊を取り上げる義務はない」。
これは出版業界では、不穏・不遜な発言です。
新聞・雑誌など商業出版での書評という制度は、基本的に「新刊」を取り上げることに、経済的な意義があります。書評で取り上げられた本を取次が積極的に本屋に卸し、本屋は良い場所に並べる。そうすると売れる。自治体の図書館も、購入する際に書評を参考にする。
新刊でないものを取り上げると、在庫がなかったり、取り寄せるのに時間がかかったりして、本屋で目立つところに置かれるまでにタイムラグが出るので、あまり効果がない。
書評欄がある新聞・雑誌には、出版社は新刊を無料で送ってきたりして便宜を図る。書評欄が充実している新聞・雑誌には出版社は本の広告も出す。そうやって新聞・雑誌と出版社の間の持ちつ持たれつの関係ができ、取次や本屋や自治体図書館を含めた商売のサイクルができる。
書評の書き手とは、そういう商売のサイクルの一端を担っているのです。純然たる商行為の歯車である、というところは否めません。
その立場を拒否する「新刊は取り上げないかもよ」という条件は、「じゃ連載は止めてください」と言われても仕方がないものです。
逆に私から言えば、現在の新聞・雑誌の媒体で、報酬面なども含めて、従来型の制度の末端の「歯車」としての書評の書き手になるインセンティブがあるかというと、全然ありません。
ですので、まず「新刊本でなくてもいい」という条件は、譲れないものです。なんでたいしたことがない本を苦労して紹介しなければならないのか。その時間があれば他のことに頭を絞れます。
しかしそれだけにとどまらず、上記の引用を見ていただきたいのですが、私は「日本語の本でなくてもいい」という条件を付けています。
これは日本の出版業界では、もはや宇宙人のような発言です。
出版の技術として多言語対応が困難であるだけでなく、言語の壁は、日本の新聞・雑誌・出版の世界を守る非関税障壁のようなものです。
しかし英語での世界の議論がまるで存在しないかのようにふるまえる日本の言論空間・知的社会教育の行き詰まりと限界は、言語で守られたメディア・出版業界が固定化してきたものでもあり、書評欄という制度もそれを支える一つの部分でありました。その意味で、日本の言論をましなものにするには、多言語空間へのインターフェースを作る必要があります。別に日本人同士が英語でやり取りしなくていいですが、英語圏で先進的な知見については、タイムラグなく同期していける仕組みが必要です。
しかし読書日記で、あるテーマを取り上げ、「これについては日本語では読むべき本がないので、英語で最新の○○、シンクタンクの報告書××を紹介します」と書いた場合、英語の本はすぐに読みたければアマゾンで注文するでしょう。いっそアマゾンの電子書籍を買ってダウンロードしてしまうかもしれません。英語圏のシンクタンクの報告書はほぼタダでダウンロードできます。
そうなると、この書評によって、日本の出版社にも、取次にも、本屋にも(あと著者にも)、一円もお金が落ちません。税金すらおそらくほとんど日本政府に入らないでしょう。
そうなると、日本の国民経済を死守する立場からは、そのような書評は、おおげさに言うと、「非国民」扱いをされかねないものです。
しかし、国民の知的水準の向上という意味では、この書評には公益性があります。日本の非関税・言語障壁で遮られた空間で、一流でない知的産物を国民が売りつけられて消費している場合と、最先端のものを外国語であれ苦心して求めて摂取している場合とで、どちらの国民が文化的に進んでいるでしょうか。後者でしょう。
出版やメディアが「単なる商売ではない=何らかの公益性がある」とみなすならば、必要なときは後者の経路を可能にする、積極的に支えるものでなければなりません。それを排除するカルテルを結んだりするのであれば、その業界は公益性のない、単なる私益・利権集団ということになります。そういうものがあってもかまいませんが、税制優遇とか、規制による保護とか、かつて行われた政府資産の優先的払下げ割り当てとか、再考しないといけない面が出てくるでしょうね(ギラリ)。
英語の本を紹介しても日本の企業に一円もお金が落ちない、という状況は、そもそも洋書を取り扱う日本の書店が長くカルテルを結び、もっぱらの書い手であった大学に対して法外なレート換算で売りつけ、それを買わざるを得ないようにする役所の書類制度に守られてきたからです。そこに安住している間にアマゾン黒船がやってきて、個人で洋書を買いたい人向けに便利で安価なシステムを提供し、新たな市場を開拓したうえで独占してしまいました。誰が悪いかというと、まあ税金払わないようなシステムを作るアマゾンも悪いですが、カルテルを結んで役所と結託していた洋書屋さん業界がより悪いのです。品揃えも悪く持ってくるのも遅く高い、というどうしようもないものだったのですから。
ですので、そういった業界のしがらみは気にせず、外国語の本もこの読書案内では紹介する。本屋さんは洋書の読書案内を見て洋書コーナーを充実させればいいじゃないですか。それをせずに、「日本語の本を紹介しないこのコーナーは駄目だ」と出版社・本屋が言って、編集部が「そうでございます。これからは日本語の本を書評させますからどうかひとつその」とか言って何か言ってくるようになったら、私としては執筆する意味はなくなります。
もちろん本当は日本語の本を紹介したいんですよ。でも、あるテーマについて、今最も適切な本を示す、という最低の基準は維持しなければならない。単に日本語の市場に出ているから宣伝します、ということをやらないといけないのであれば、あのそれは非常に純然たる商行為ですから、現在の日本の原稿料相場では私は書けませんよ。絶対やらない、とは言わないが「要相談」という別の話になってしまう(=やりませんよ)。
(0)『エコノミスト』読書日記の第1回の発売日は4月28日(5月6日号)
さて、このようにすでに本質的なところは書いてしまっていたのだが、連載第1回の前にもう一度告知した。私の初回の発売日が1週違っていたから。原稿の締め切りからタイムラグがあるんですな。それがウェブ媒体に慣れた現在ではもう想像できなくなっている。報道記事はぎりぎりまで締め切りを延ばすのだろうけど、連載の文化欄は早めに原稿を取っておくというのが新聞・雑誌業界の慣行。でも私の場合は書評でも時事問題を絡めたりするので、あんまりタイムラグがあると書きにくいという問題はある。まあなんとかなるが。
このように現存の制度の「悪いところ」をいろいろ書いてしまいましたが、わざわざ時間と労力を使って読書日記の企画に踏み出そうとするのですから、もっと肯定的な目標があるのです。英語圏の議論やウェブのコンテンツにも視野を広げた読書日記の新企画を、あえて日本語の経済週刊誌の紙の媒体でやるというのも、考えがあってのことです。
まず、文章技術としては、制約がある方が面白い。
従来型の新聞・雑誌の書評・読書日記を、日本語の新刊本についてやるだけなら、流れ作業のようなものです。そこではもう能力の発達は望めない。面白い本に巡り合うよりも、無理に推薦する労働の苦痛ばかりが降ってくるでしょう。
また、逆に、ウェブで書くなら、多言語だろうがリンクだろうが自由自在に貼れます。好きな本も選べます。しかしウェブの媒体であれば読んでくれる人は、すでに「こちら側」にいる人です。リンクを踏んで英語や、やむを得ない場合はアラビア語などに飛んで行かされても苦にしない人が読んでいるのです。
それに対して、紙の媒体をなおも手にしてくれる人は、ある意味得難く、貴重です。ウェブや英語にはなかなか行かないけれども、紙の本には自然にすぐに目を移してくれる人たちなのです。そうであれば、必然的な制約があっても、紙の媒体で英語にもウェブにも架橋する場所をもし作れれば、そういった読者がさらに知見を積んで、より高度な内容を本に求めるようになるかもしれない。そうなって初めて、書き手として、あるいは読み手・買い手として、より心地よい空間が生まれてくるかもしれない。
誇大妄想気味にこのような課題を設定して、連載に向かいました。
(1)読書日記1「本屋本」を読んでみる『エコノミスト』5月6・13日合併号
さて、前置きが長くてやっとたどり着いた連載第1回ですが、ここでは本屋賛歌。
モノとしての本と本屋に、どのような利点があるのか。これについて数多の「本屋本」からセレクトして、
福嶋聡『紙の本は、滅びない』(ポプラ新書)
内沼晋太郎『本の逆襲』(朝日出版社)
を選びました。
いずれも、紙の本と本屋を絶対視していない。ウェブに面白いものはいくらでも転がっており、本屋でも新刊本屋と古本屋の両方の選択肢があり、図書館と言う選択肢もあり、という前提の上で、あえてなお紙の本と本屋にはどんな意義があるのか、積極的に問い直してみる。前向きの本です。
(2)週刊エコノミストの読書日記(第2回)~新書を考える
しかし第2回は暗転。実際にそこいらの本屋に行ってみると、読みたい本にたどり着けない。ジャンクフードのような刹那的な本が溢れている。だから、この回は良い本を推薦するという形式ではない。ジャンクフードのジャンクフードたるゆえんはどのような本に現われているか。
だいたい日本の書評の慣行は、批判してはいけないというものです。新聞の書評などでは、特にその縛りがあります。なぜって、すでに書きましたが、商売の歯車だからです。良いものを売れるように一肌脱ぐのは大歓迎ですが、良くないものまでなんで宣伝しないといけないのか、さっぱり分からない。いえ、ぶっちゃけた話、「新聞に書評書いてると、知名度上がりますよ、本も送ってくるようになりますよ」というのが誰も言わないけど過酷な労働条件を呑ませるために提示された給付の暗黙のリストの中に入っているのですが、実態としてこの効果はもはや疑わしい。ちゃんとした文章ならブログで書いている方が効果はあるんじゃないかな。誰を相手に書くかにもよるけど。
まあしかしジャンクフード紹介、では読書日記欄がすさむので、ちょうどその時、別件で頼まれていた、ちくま新書のリストを全部見て1冊お気に入りを紹介という仕事を流用して、リストを見たら載っているこんなにいい本、という趣旨で新書の良書を列挙しておいた。これについてはまた別のところで書こう。
(3)読書日記の第3回は、モノとしての本の儚さと強さ
第3回は、今度は電子書籍論。ただし、電子書籍のパラドクス。
肝心な時に肝心な本が手に入らない。国際情勢が激変して、ウクライナ問題とか、「イスラーム国」とか、想像もしないことが生じたときに、粗製乱造の解説本は出るかもしれないが、本当のことをずっと前に書いていたような本は、絶版・品切れで市場のどこにもなかったりする。
じゃ、全ての本が電子書籍でも出ていれば、手に入らなくなる可能性もないよね?
でもよく考えてみるとそうでもない可能性があります。
人はなぜモノとしての本を買うのか。前提として、「買っておかないとなくなってしまうから」というものがあります。紙の本は、モノである以上、可能性としては水に濡れたり火にくべてしまえば損壊・消滅しますし、売れてしまえば市場になくなる。高価な学術書になると、もともとの部数が少なく、高いので専門家にしか売れないとなると増版もされない。
逆に言えば、だからこそ買っておくわけです。
電子書籍もあるから必要な時が来たらいつでも買えるよ、ということになると紙の本は買わなくなるでしょう。そして、電子書籍も結局買わない。なぜならば、「必要な時」が認識されるような本はごく稀だから。
だったら本って、出なくなりますよね・・・・
(4)週刊エコノミストの読書日記(第4回)学術出版の論理は欧米と日本でこんなに違う
じゃあどうしたらいいんだ、と考えるときに、参考になるのが英語圏の学術出版。学界・大学出版・大学図書館というトライアングルが強固に出来上がっていて、そこで書き手の質が維持され、出版社への利益が確保され、必要な読み手によるアクセスが保障される。必要な読み手とは必ずしも世間一般の読者ではない。大学院生を含めた専門家です。
一般読者の選好を基本的に意識せずに本を作り、売り、届けることができる英語圏のシステムは、一定の規模の学術出版の世界を成立させると共に、社会に知を広めるのにも役割を負っています。ただし、一般読者が単に興味を持って読みたい、という時にフレンドリーかと言うと、そうではないでしょう。一定のディシプリンを身につけていないと読み解けないようなルールの下に本が書かれ、大学院に所属していればどの本もほぼ借り出せるし、大学のアカウントからオンラインで読める場合もある。その対価・使用料が著者や大学出版に入る仕組みになっている。
日本がすべて真似しなければいけないわけでもないし、真似もできないだろうけれども、専門的な出版の質と規模を確保するためには、現存する最も高度な仕組みであることは確かだ。そこから漏れる部分もあるけれども。
逆に、日本の場合は、学術出版も多くの場合は商業出版社が行っているから、どうしても消費者の意向(と編集者やら「営業」や、一般的に上の方にいるおじさんたちが「消費者の意向」と信じているもの)に左右されがちだ。もちろん博士論文を出版した、というような固いものもあるけれど、それではその次に本当に出版として意味のあるものを書いて出せるかというと、多くの学者がそのような「書き手」になるには至らない。義務としての最低限の出版をしてからは、出版の世界から退出してしまう。確かに、純然たる商業出版の要請に応えるタイプの芸を持っている人は少ないし、分野によってはまったくお呼びがかからない。学術出版のもっと自立したサイクルがあれば、その中で切磋琢磨して着実に書いていけそうな人たちはいるのだけれども。
そのため、商業出版の要請に応える才覚というか軽率さのある一部の書き手が、新書を中心に膨大な量を生産することになる。そこには、学術的知見をタイムリーに要領よくまとめてくれて刺激になるものもあるが、「もう少し考えればもっといい本になったんじゃないの?」「よく知らないことについて書かない方がいいんじゃないの?」と言いたくなるものが大半だ。要するに、話題になってから急ごしらえで本を作る。それに対応できる、してしまう一部の人だけが請け負って、劣悪な労働条件で商業出版のライターの役割を果たすわけである。日本の学術的知見の多くは、実際には商業出版によって消費者動向に従って出版される。
このような日米の学術出版を対比するのには、日本を「需要牽引型」で、米国を「供給推進型」ととらえるといいのではないか?と普段一部の研究者や編集者との与太話で提案している学説をここで活字にしてしまった。
* * *
さて、こんな感じで、大きなパズルの各所に、最初の小さなピースをいくつか置いてみた、というのが連載の現状。そこで今回は別方向に、自分のルーツをたどるという趣向で、市場の商品、制度の産物という側面とは別の、パーソナルな部分での本との結びつきについて、発端を書いてみた。自分の事ばかり書くのは好きではないので、めったにこの話題には戻ってこないけれども、これまでに公の場で全く書いていないいろいろなことがある。そのうち色々書いてみたい。
今後どうなるんでしょうね。どういう形であれ、連載の依頼を受けたことで刺激を受けて始めてしまった、新しい形の読書論、ゆっくり育てていこうと思っています。
なお、この連載は『週刊エコノミスト』の電子版を契約していただいても読めません。毎日新聞社が提示してくるデジタル版の契約条件が私の基準と合わないので、承諾していないのです。ですので、もし連載が今後も続いて、ご関心がある方は、刊行された週に、本屋でお買い求めください。
私の電子出版に関する基準はいろいろありますが、儲けようとかいうことではなく、「そのやり方で、出版は成長しますか?市場は開拓されますか?本当に考えてやっていますか?」ということを第一に考えたうえで判断している。
大前提は、連載の第3回で書いたことに関わります。「いつでも買えるなら、今週出たものを今買うインセンティブはなくなる」。そして、ウェブ雑誌の形ではなく紙の雑誌のそのままのフォーマットでしかデジタル版が提供されていない場合は、要するに「バックナンバーを買う」のと同様になるのです。実際には、バックナンバーを買う人はあまりいないでしょう。それにもかかわらず、デジタル契約を許諾してしまうと、半永久的に電子版複製の権利が出版社に保持される。かえって流通を阻害します。
紙版はその点良いのですね。なぜならば、モノとしての本・雑誌は、抱え込んでいるとお金がかかるから、やがて絶版になるか、あるいは売り切ってなくなる。出版社の権利とは出版をし続ける義務を伴いますから、絶版・品切れになれば出版社側の権利はほぼ消滅する。作品は、少なくともテキスト部分は、自由に新しい道を歩み出せるのです。電子データは保存するコストが極小なために(そもそも実際に一部ずつ売れるまでは、「存在しない」のだから)、有用な売り方を出版社が知恵を絞って考えたり、もう売れないから絶版にするという判断をするといった労力を省かせ、かえって作品が塩漬けになる可能性があります。