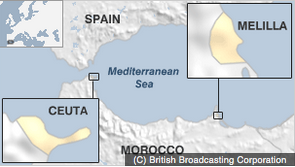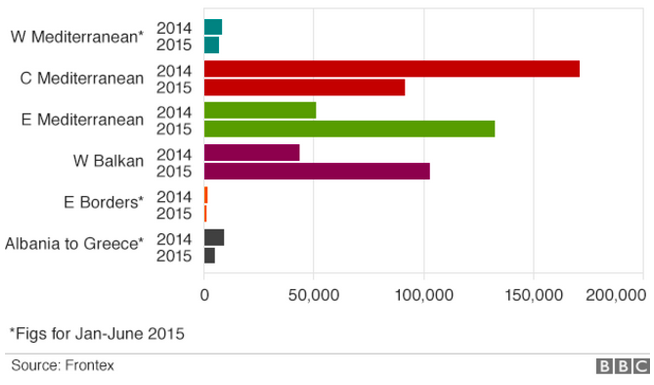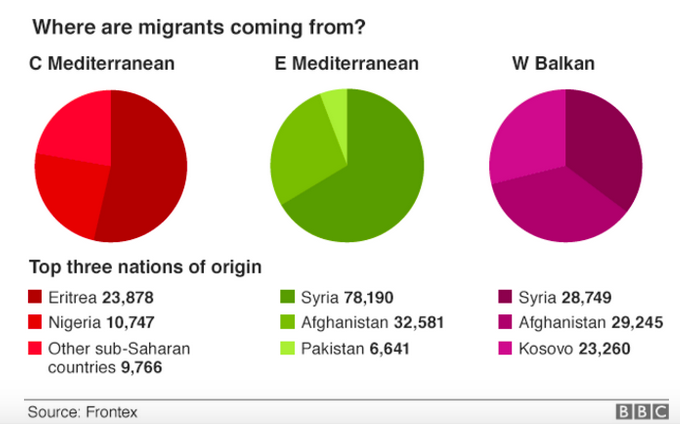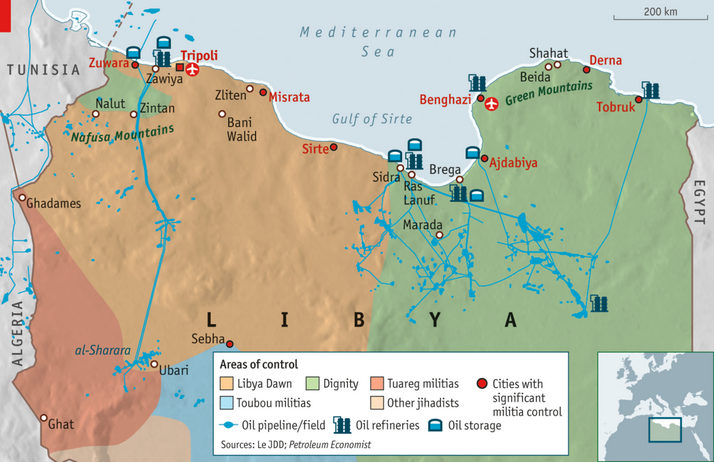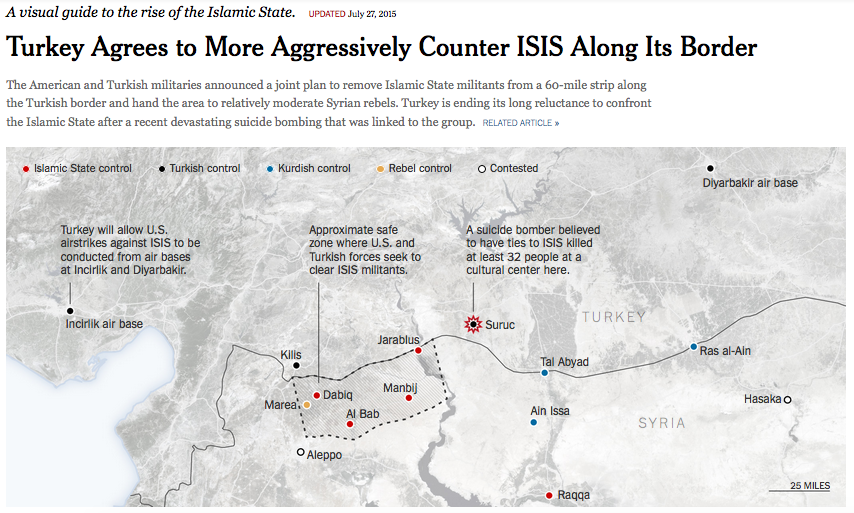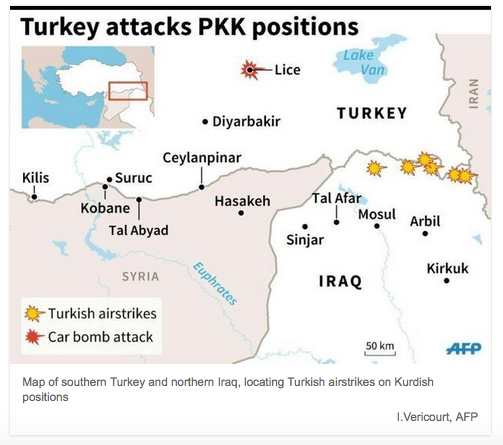あんまり時間がたたないうちに書いておこう。
4月11日に、イギリスの著名な中東ジャーナリストのパトリック・シールが亡くなった。1930年生まれで、享年83歳。

代表作はAsad: The Struggle for the Middle East, 1988.
今のシリアのバッシャール・アサド大統領の父親、ハーフィズ・アサド前大統領の評伝で、シリア現代政治史の一級資料とされる。この本自体はいわゆる学術書の体裁は取っていないが、どんな研究書でも必ず言及・引用される本だ。(もちろん日本のジャーナリストの作品と比べれば、文献の参照の仕方も引用の仕方も、格段に学術的な方法で書かれているのだが)。
アサド前大統領本人を含むシリアの政権・支配階層と親交を深めて、アサドの来歴・人物像と、アサド体制の在り方を明らかにした。秘密に閉ざされた独裁政権の存立根拠を知るために、最適の本となっている。今後も参照され続けるだろう。
他にも著名な作品がいくつもある。
The Struggle for Syria, 1965から始まったシールの著作家としてのキャリアは、レバノン建国の父リヤード・アッ=スルフの評伝、The Struggle for Arab Independence: Riad el-Solh and the Makers of the Modern Middle East, 2010まで続いた。2011年以来のシリア内戦に際しても、イギリスや国際的なメディアに姿を現して解説することも多かった。亡くなったと聞いてちょっと驚いた。
彼の文章のスタイル自体が、パトリック・シールの人となりを十分に表しているとは思うのだけれども、英語圏のインテリの間ではよく知られている彼の来歴やエピソードを記せば、より何かが伝わるかと思う。
この人は、「かつての」欧米の中東研究がどういうものであったか、身をもって示している。広く言えば、オリエンタリズムの伝統の中での現代中東研究という、一つの重要な流れだが、そこにはイギリスのエリート・上流社会(そしてそこに連なろうとする一時期の米国の上流社会を含めて)の精粋というべき華やかな光の部分と、同時に、少なくとも私から見れば、嫌~な影の部分、あるいは残酷な日常の両方が、現れている。
欧米の中東研究の厚みというものは、欧米諸国が国として、社会として、文化として、中東の国家と社会と文化に深く絡み合ってきたところに由来する。そのことを忘れて、現地のアラブ社会やイラン社会などの表面上の民族主義的な言説に囚われると、現実を見失う。あまりに欧米の影響が強いから、それを否定する民族主義的言説も強まるのであって、反欧米の言説の存在は、現実の社会が欧米とかけ離れているとか無縁でありうることを全く意味しない。
だから、中東に興味を持つ際には、日本人のぼんやりした欧米への反感・コンプレックスを中東の「民衆」に託さないでください、というのが短期的にはアドバイスなのだけど、そういう日本独自の問題はここではもはやどうでもいい。
この欧米と中東との骨がらみの関係を知るということがまず第一に重要なことだ。
植民地時代が遠ざかるにつれて、欧米と中東との関係は薄れてはいるが、形を変えて残っている。根っこにはどのような関係があってそれが今でもどのように影響を与えているかを窺い知るには、幾人かの、際立った個性を持った、欧米社会の中で突出し、世間の耳目を集めてきた人たちが、どのように中東とかかわっていたかを知ることが、大きなヒントとなる。
イギリスやアメリカには、何人か同じような系統の人がいるけれども・・・今回はパトリック・シールについて。
イギリスの新聞のObituaryは格調高く、胸を打つものが多い。ガーディアンと(系列の日曜紙)オブザーバーに、同じ筆者が二つ書き分けているので、まずこれらを見てみよう。パトリック・シールはもともとオブザーバー紙の中東特派員だった。
まず彼の生まれ。オブザーバーの方では簡潔にこう書かれている。
Seale was born in Belfast in May 1930 but spent the first 15 years of his life in Syria, where his father Morris was a Christian missionary. He became irredeemably fascinated by the Levant.
北アイルランドのベルファスト生まれ。父が宣教師で赴いたレバント地方(シリアやレバノン)で幼少期を過ごした。
これらは重要な情報ですね。欧米の、年配世代の中東専門家は、第一次大戦後に植民地となったシリア・レバノンに出向いた宣教師や植民地行政官の子息が多い。小さいうちにアラビア語を身に着けつつ、欧米のエリート社会に根っこを持つ。エリート社会の生まれと言っても、本国に残って安楽な生活をするのではなく、冒険心や宣教意欲などが活発な、活動的な人の家庭で育ったということも、人格に影響を与えているだろう。
ガーディアンにはもっと踏み込んで来歴が書いてある。
Born in Belfast, Patrick was the son of Reine Attal, a midwife of Tunisian-Italian origin, and the Arabist and biblical scholar Morris Seale. Shortly after his birth the family moved to Syria, where for 20 years they ran the Irish Presbyterian mission. Patrick grew up between the Old City of Damascus and the mountain village of Bloudan, places and people in a landscape that would forever entrance him during the final years of Syria’s deeply resented French Mandate rule.
お父さんは宣教師だったが、お母さんにももともと北アフリカの血が入っていたのですね。単にシリア・レバノンで育っただけでなく、チュニジア人とイタリア人の混血という、当時はごく普通でもあった地中海世界を横断して行き来する人の流れと、母を通じてつながっている。当然、視野は地中海世界全体、アラブ世界全体に広がるだろう。
また、お父さんが宣教師でありつつアラビスト・聖書研究者であったとも書かれている。学者肌の人だったんですね。
また、北アイルランド生まれだけど、プロテスタント、というところも意味深い。北アイルランドの複雑で緊張した社会の中で、もともとが支配する側だったんですね。もちろんどういう経緯で父がアイルランドに住んでいたのかは分からないけれども。
カトリックとプロテスタントの紛争の最前線に生まれたともいえる。それがパトリックが生まれてすぐ家族でシリアに移住し、(カソリックの)フランスの支配の下にあったシリアでプロテスタントの宣教活動に従事している。今度は英仏の植民地競争の最前線に移ったわけだ。大戦と、宗派紛争や民族独立闘争も目にしているだろう。
ここまでが出自で、十分に劇的ですが、その後の人生はもっと陰影に富む。
例えば、キム・フィルビーとの関係。
In the early 1960s, he worked in Beirut as a freelance contributor to the Economist and the Observer. That paper’s Middle East correspondent, based in the city, was Seale’s friend Kim Philby, the British agent shared by MI6 and the KGB. Seale’s break came in 1963 when Philby fled to Moscow. Seale was awarded the Observer posting, though did not use it as cover for being an MI6 operative.
単にオブザーバーの特派員だった、というわけではなくて、あの有名な二重スパイ(イギリスのMI6の諜報員として活動しながら、実際にはソ連KGBのスパイだった)の「キム・フィルビーと親交があり、かの有名なソ連への亡命後には、後任の特派員となった」という点が、彼の経歴に彩りを与えている。
「ただしMI6には入らなかったよ」と書かれていますが、世間のイメージ的にはスパイ映画の主人公みたいな人なんですね。
イギリスのスパイ(風の人)ということになると、学歴はほぼ想像がつく。オックスフォードかケンブリッジです。キム・フィルビーは「ケンブリッジ5人組」の一人だが、シールはオックスフォード。しかしそれに至る過程も見ると面白い。
He was educated at the French lycee in Damascus and at Monkton Combe school, near Bath, a haven for sons of the clergy. After a national service commission, part of which he spent in a tent in the Suez Canal Zone and most of the rest in the Intelligence Corps, Seale studied philosophy and psychology at Balliol College, Oxford (1950-53).
第二次大戦直後の時期と思われますが、徴兵でスエズ運河地帯で過ごすとともに、やっぱりインテリジェンス部隊に配属されていますね。宣教師の家庭に生まれてかつ中東に、それもフランス統治下のシリアに一家で住んでいたのですから、ラテン語、ヘブライ語およびフランス語、アラビア語の言語能力には長けていたでしょう。最適の人材ではあります。それをもってその後の人生においてスパイとして活動していたと決めつけることはできませんが、そのような人材であったとはいえるでしょう。
で、名門のオックスフォード大学ベリオール・カレッジに学んでいます。
At the end of the decade he returned to Oxford to pursue Middle East studies at St Antony’s College.
大学院で、中東など国際関係に強いセント・アントニーズ・カレッジでも学んでいます。
ここまでは基礎編。
上級編は?
よく知られた「あのこと」はどこに書いてあるんだろう。
「あのこと」というのは、奥さんと娘さんのこと。
オブザーバーの末尾には簡潔にこのように。
He married twice: Lamorna Heath in 1971, who died in 1978, mother of Orlando and Delilah; and Rana Kabbani, from whom he was separated, mother of Alexander and Jasmine.
ガーディアンでは、より詳しく、
Seale married Lamorna Heath in 1971; she died in 1978. Seven years later, he married Rana Kabbani; they eventually separated. She survives him, as do their children Alexander and Yasmine, and Orlando and Delilah, the children of his first marriage.
とありますが、肝心なことが書いてないな。
負の側面や批判的なことも書くイギリスのObituaryも、男女関係のややこしい話については遠慮するのですね。一つ勉強になりました。
ためしにフィナンシャル・タイムズを見ると、私生活については一切書いていない。
なお、フィナンシャル・タイムズの末尾の
Patrick Seale wrote history in the grand style.
という一言はなかなか良いですね。
話を戻すと、私生活について、上品なガーディアンやビジネス誌のフィナンシャル・タイムズでは書かないにしてもよそではどうなっているんだろう。もうちょっと大衆的な(純然大衆紙ではないですけれども)テレグラフを見ると、、、書いてありましたよ。控えめですけれども。
In 1971 Patrick Seale married Lamorna Heath, who died by her own hand seven years later after producing a son and a daughter. It turned out that the daughter, Delilah, was actually fathered by the novelist Martin Amis. Seale told Delilah (and Amis) the truth when she was 18.
さらっと書いてるけれども、かなりの悲劇を私生活で体験してきた人だということは分かりますね。「1971年にラモーナ・ヒースと結婚したけれども、彼女は7年後に自殺した。息子一人、娘一人を残して。娘の方は、実際には小説家のマーティン・エイミスが父だった。シールはそのことを娘が18歳の時に告げた」。
ものすごく端折っているので、なんだかすごいひどいことが行われたという印象をかえって強く受けるような文章ですね。
しかも、娘の名前が「デリラ」・・・・
娘にそんな名前つけるかあ?
デリラというのは、旧約聖書に出てくるサムソンの妻。サムソンは古代イスラエルのヘブライ人の士師(指導者)で怪力の持ち主。ヘブライ人を糾合してペリシテ人の支配を退ける。ペリシテ人がサムソンを倒そうと虎視眈々と狙っているが倒せない。しかしサムソンはペリシテ人のデリラと恋に落ちる。サムソンの弱点は、その髪を切ると怪力が失われること。デリラはサムソンを誘惑してそれを聞き出し、夫が寝ている間に髪を切ってしまう。ペリシテ人たちはサムソンを捕え、両目をえぐり、ガザの牢獄に繋いで、石臼を挽かせる。サムソンは神に祈る。やがて髪が再び伸びだし、怪力を取り戻したサムソンは、つながれていた鎖を引きちぎり、建物の柱を倒して崩壊させ、ペリシテ人たちを皆殺しにする・・・・
聖書の中でも際立って酷薄で陰惨で妖艶な物語です。
サン=サーンス作曲のオペラ「サムソンとデリラ」でも有名です。映画もありました。
実は私、小学生の時に、父親がプログラムに解説を書いたか何かでチケットが回ってきて、このオペラを見に行かされたことがあって、全然意味分かりませんでしたが、石臼に繋がれて暗闇で呻吟するサムソンの唸り声、最後に盲目のサムソンが力を振り絞って大伽藍を崩壊させる時の大音響、ペリシテ人たちの阿鼻叫喚の声、だけが記憶に残っています。子供に見せるようなものではありません。トラウマになりますね。
「デリラちゃん」の命名で度肝を抜かれてしまいましたが、そもそもその出生が尋常でなかったですね。ええと、母は1971年にパトリック・シールと結婚したんだけど、7年後の1978年に母は自殺して、実はデリラちゃんはシールとの間の子供ではない?相手はマーチン・エイミスとかいう作家?
このあたりは、「イギリスの読者は知っているから書かない」という部分と「追悼文だからあえて書かない」ところが混じって分かりにくいです。ですので、下世話で不謹慎ですが、パトリック・シール+デリラとかで検索してみると、出てきます。
デリラさんについての記事。まず、あんまり下世話ではないガーディアンの記事にしましょう。
“My long lost dad, Martin Amis,” The Guardian, 26 February 2011.
Her own family narrative has been rather more complex. When Delilah was two, and her brother, Orlando, three, their mother, Lamorna Heath, hanged herself. Heath, a writer, had had depression for many years. Her husband, the writer Patrick Seale, was left to bring up the two children alone, which he did, in spite of having learned, a few months after Delilah’s birth, that he was not her father. During a short period when he and Heath were separated, Heath had had an affair with the novelist Martin Amis, and Delilah was the result.
デリラさんが二歳の時に母は首を吊った・・・それだけで怖いですが、勇気を振り絞って先を読んでみましょう。彼女はこの時まだ2歳。
あれ、年齢が合いませんね。お母さんのラモーナ・ヒースさんがパトリック・シールと結婚したのは1971年で自殺したのが1978年のはずでしたが。亡くなった時にデリラさんはまだ2歳で、しかし父親が違う?
During a short period when he and Heath were separated, Heath had had an affair with the novelist Martin Amis, and Delilah was the result.
お母さんが家を出ていた時期というか不倫していたというか、私のようなお子様にはよく分からな~いオトナの事情があった上で戻ってきたお母さんはデリラを身に宿していた。パトリックはそれを受け入れ、自分の子として育てた・・・
まあ、二人(三人)の間のことですから、そこにどのような事情があったのかは、分かりませんけれども。ヒースさんは戻ってきて3年後には自殺しているわけですよね。
デリラさんの実の父のマーティン・エイミスは、パトリック・シールよりももっと有名な作家です。
マーティン・エイミスは自伝でこの件について触れているようです。
Amis knew about her. As he wrote in his autobiography, Experience, Heath had told him and had given him a photograph. “It showed a two-year-old girl in a dark flower dress, smocked at the chest, with short puffed sleeves and pink trim. She had fine blond hair. Her smile was demure: pleased, but quietly pleased.”
ガーディアンの記事ですから、上品に書いてありますね。
しかしマーティン・エイミスという作家、有名ですが、そんなに評判の良い作家ではありません。悪名高きというべきか、いや、それこそ悪名ばかりが高いというべきか。
もっと大衆的な新聞を読んでみましょう。
“Martin Amis’s lovers laid bare,” Evening Standard, 2 June 2009.
「マーティン・エイミスの恋人を暴露する」。「暴露する」が「裸にする」をも意味する表現で、まあ、お下品。
そこで過去のスキャンダルのうち有名なものをいくつか列挙されているのだが、そこでデリラさんの名前が挙げられている。
Delilah Seale
Learned Amis was her father on the night of her A-level results when journalist Patrick Seale, who had brought her up, broke the news over dinner. “I cried and cried,” she wrote. Met Amis a year later after exchanging letters in which he told how he had decided not to be part of her life. Now a 33-year-old television producer living in west London.
Aレベル試験というのはイギリスの高校卒業資格試験=大学入学試験のことだが、その結果が出た嬉しい日の夕食の席で、大人になった日ということでもあるのか、育ての父パトリックはデリラに出生の秘密を明かした。何もそんな日に教えてくれなくっても・・・
デリラさんは “I cried and cried.”
大衆紙らしい単調なお涙ちょうだいの表現ですが、痛ましい話であることは確かです。
ここは多分に想像ですけれども、パトリックさんは優しいけれども、複雑で、かなり残酷な一面があるんじゃないかな。そもそもデリラなんて名前、普通は付けないだろう。
しかし「デリラ」と名付けて、パトリック・シールは血の繋がっていない娘にどのような人生を送ってほしいと思っていたんですかね。異民族の権力者を誘惑し、籠絡し、欺き、裏切って、悲劇のどん底に突き落とし、それが原因で最後は自らの国を崩壊させる?
実の名前というよりタレントの芸名ならあるかもしれませんが。
娘さんの方は自分の名前の意味を分かるようになると、呪いでもかけられたように感じるのではないかと心配しますがどうでしょうか。
デリラさんはテレビ業界に勤めていて、写真を見るとなかなかきれいな人であって、それでゴシップ紙にしょっちゅう取り上げられているのでしょうね。で、常に「マーティン・エイミスの子」「母親は不倫の末自殺」と言われ続ける。
その際に、「影」のような人物としてパトリック・シールは取り上げられるということなんですね。中東専門家として世界中の学生に知られているシールさんですが、イギリスでは、奥さんが有名な作家とあんなことがあってこんなことがあった人なんだよ、と常に語られてしまう人でもあったんですね。
しかしマーティン・エイミスって、確かに名前は聞いたことあるけれども、どんな作品書いていたっけ?というと思いつかない。
こんな記事を読むと、
Martin Amis is the most argued about novelist in the United Kingdom, largely, I suspect, because hardly anyone reads him.
「エイミスはイギリスで最も議論の的になる小説家だ。なぜかというと、誰も彼の小説を読んじゃいないからだ」なんて書かれているので、私が不勉強というだけではないようだ。要するに作品よりも私生活で有名な人。
この記事のタイトル”Martin Amis: The Mick Jagger of letters(マーティン・エイミス──文学のミック・ジャガー)”がすべてを物語っているんでしょうな。
マーティン・エイミスは、お父さんが著名作家のキングズレイ・エイミス(Kingsley Amis)という、毛並みの良い二世作家。先ほどのイブニング・スタンダードの記事によると、実はマーティンは大学生の途中まであんまりイケてなくて、しかしティナ・ブラウンという、後にニューヨーカーとかヴァニティ・フェアとかの編集者になったセンスのいい女性と付き合ってから開眼して「文学のミック・ジャガー」になったそうな。開眼したといっても「文学に」というよりは「ミック・ジャガー方面に」なんでしょうけど、と突っ込みを入れたくなるのは私がずっとイケてないままだからか。たぶんそうです。
In 2007, he revealed that it was Tina Brown, former editor of Tatler, the New Yorker and Vanity Fair, who made him the man he is today and he credited her with transforming him into a literary Mick Jagger.
The romance began when he was 23 and she was a 19-year-old undergraduate at St Anne’s College, Oxford. “She was and is adorable,” he said.
Amis was the son of Lucky Jim author Kingsley Amis and had graduated with a First in English from Exeter College, Oxford. After Brown, he went on to squire some of the most eligible women of his generation.
学歴はやっぱりオックスフォードだそうです。オックスフォード出の人たちの中でぐるぐる回っている人間関係なんですね。マーティン・エイミスは1949年生まれ。パトリック・シールより19歳も年下なのか・・・
なお、パトリック・シールは再婚して、そして離婚しているのだが、その相手の名前を見ると中東研究者にはピンとくる。
テレグラフの追悼文では、次のようにあります。
In 1985 he married Rana Kabbani, a Syrian from whom he was later separated. He is survived by his second wife and by four children, two from each marriage.
ラナ・カッパ―ニーさんという、シールの次の奥さんは、調べてみるとやはり、ニザール・カッバーニーという、シリアの近代史上最大の詩人の姪のようです。
かつてのイギリスの中東専門家というのは、イギリスの上流・エリート社会の文化に根差していた。もちろんすごい主流というよりは、ちょっと脇の方の「影」の方なんだけれども。それでも社会の注目を集める人士であることは確かだ。彼らは植民地支配や世界大戦を背景に中東に渡って経験を積み、現地の上流・エリート階級と交じり合った。欧米の植民地的な中東への進出は、双方の上流階級を結合させることで、現地の民族が国家として独立した後も、影響力を保っているのです。シールさんは元の奥さんとの関係を通じて、シリアの上流階級の一部でもあるわけです。そういうところから、アサド家への排他的なアクセスも得られて、誰にも書けない本を書ける根拠になる。逆に、ラナ・カッバーニーさんにしても、イギリスのメディアでシリア問題のコメンテーターとして活躍する「セレブ」となっています。
日本で大学のアラビア語クラスで必死に単語や活用憶えて、ひげ生やしてアラブ人風にしてみて、、、などというやり方では到底敵わない世界ですね。
でもまあ、中東と関係の薄い日本から中東を見ているのは、息苦しくなくていいんですけど、個人的には。