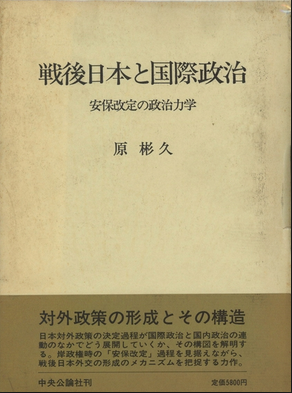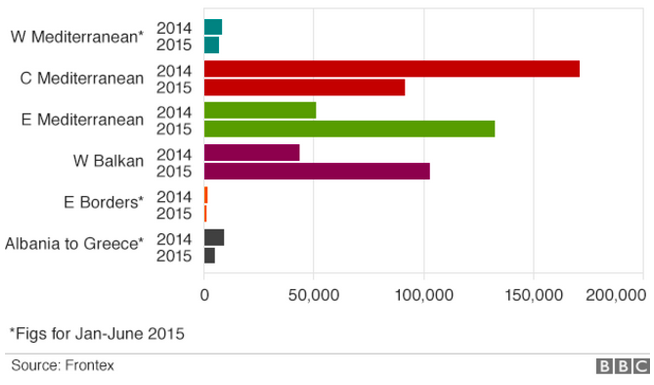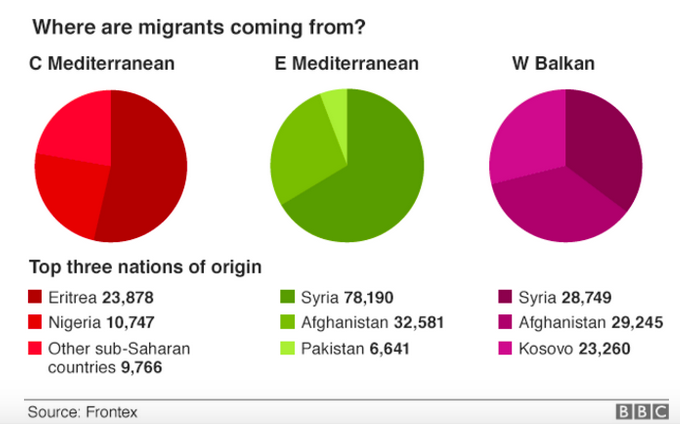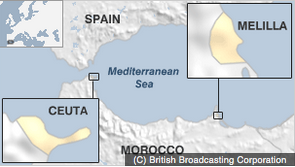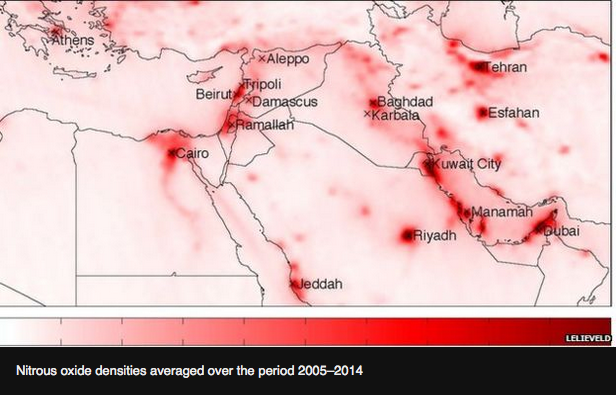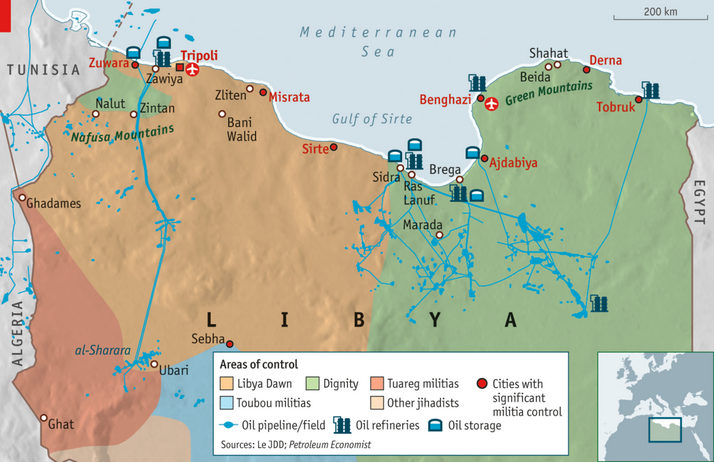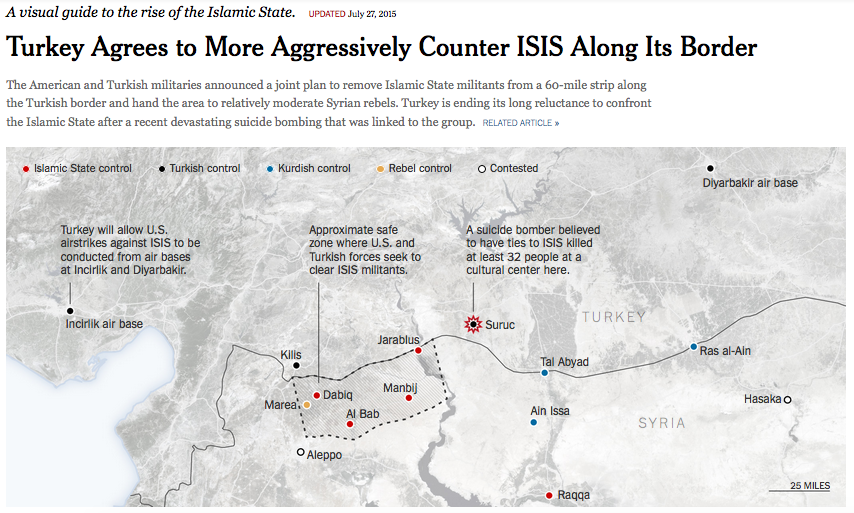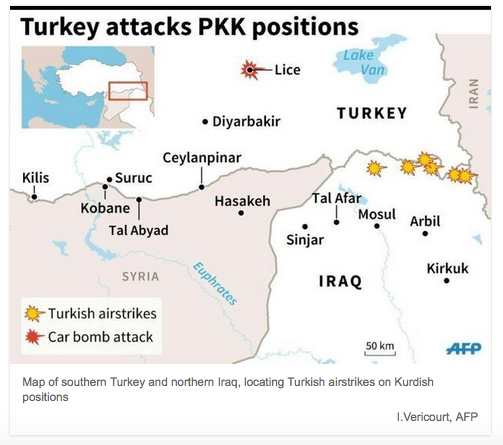さて、モーゲンソー『国際政治』を読み続けていますが、ずっと上巻だったので、今日は中巻に飛んでみましょう。
これまでのテーマの続き。イデオロギーとリアリズムの関係。
リアリズムの政治認識は勢力均衡(バランス・オブ・パワー)を原則としますが、モーゲンソーの『国際政治』で、実は勢力均衡について書いてある部分はそれほど多くないのです。多くの部分は、法や道義、慣習や国際世論を扱っています。これまでに見てきたように、モーゲンソーは、これらの理念・観念が平和をもたらすという主張に懐疑的・批判的なのですが、同時に、権力政治のみによる勢力均衡で平和が達成されるなどとも論じていません。
それどころか、第4部「国家権力の制限ーーバランス・オブ・パワー」(第11−14章)の結論部「第14章 バランス・オブ・パワーの評価」では、非常に否定的なのです。節の見出しを見てもそれはわかります。「バランス・オブ・パワーの不確実性」(中巻、91頁〜)、「バランス・オブ・パワーの非現実性」(同、101頁〜)、「バランス・オブ・パワーの不十分性」(同、116頁〜)とあるように、散々な評価です。勢力の均衡点を算出することは困難であり、各国は均衡点を見誤りかねない。であるが故に、少なくとも出し抜かれないように、力の優位を目指すことになる。勢力均衡を求めて各国は戦争をしかねない(例えば、101・102頁)。
次の部分にあるように、モーゲンソーは勢力均衡はそのままでは平和をもたらさない、と突き放しています。
「バランス・オブ・パワーがその安定化作用によって多くの戦争を避ける助けとなった、という主張は、証明することも反証することも永久に不可能であろう。人はある仮定的立場をその出発点にして歴史の道程をふり返ることはできないのである。しかし、いかに多くの戦争がバランス・オブ・パワーの範囲外で起こったかを明言できるものが誰もいない一方では、近代国際システムの誕生以来戦われた戦争のほとんどすべてがバランス・オブ・パワーのなかで起こっている、ということを知るのはむずかしいことではない。」(許世楷翻訳分担、原彬久監訳、中巻、107頁)
これに続く箇所では戦争のタイプを次のように分類して、いずれも勢力均衡の下で生じているという。
「次に挙げる戦争の三つのタイプが、バランス・オブ・パワーの力学と密接に関連している。すなわち、すでに言及した予防戦争ーーそこでは、通常両方とも帝国主義的目標を追求しているーーや反帝国主義戦争、そして帝国主義戦争そのものである。」
モーゲンソーが『国際政治』を書いた時点で(繰り返すがそれが「いつ」であるのかはこの本の成り立ち上、流動的なので、本当に正確なところはこの問題の専門家に聞いてみないといけないが)、「予防戦争」「反帝国主義戦争」「帝国主義戦争」が具体的にどのような歴史事実を指すのかは、皆様が本を手にとって読んでみてください。
しかしこの直後にもいくつか例が挙げられている。
「バランス・オブ・パワーの状況下において、一個の現状維持国ないし現状維持国同士の同盟と、一個の帝国主義国ないし帝国主義国の集団との間の対抗は非常に戦争を起こしやすい。カール五世からヒトラーおよび裕仁(ルビ:ひろひと)に至るまでの多くの実例において、彼らは実際に戦争を導いた。明らかに平和の追求に貢献し、現在もっているもののみを保持したいと思っている現状維持国は、帝国主義的膨張に専念している国家に特有の、力のダイナミックかつ敏速な増強に肩を並べていくことはほとんどできない。」(同、107−108頁)
最近では、戦後70年談話に盛り込まれて一部で話題になった、「国際秩序への挑戦者」という問題ですね。
長くなってきたので続きはまた明日にしましょう。